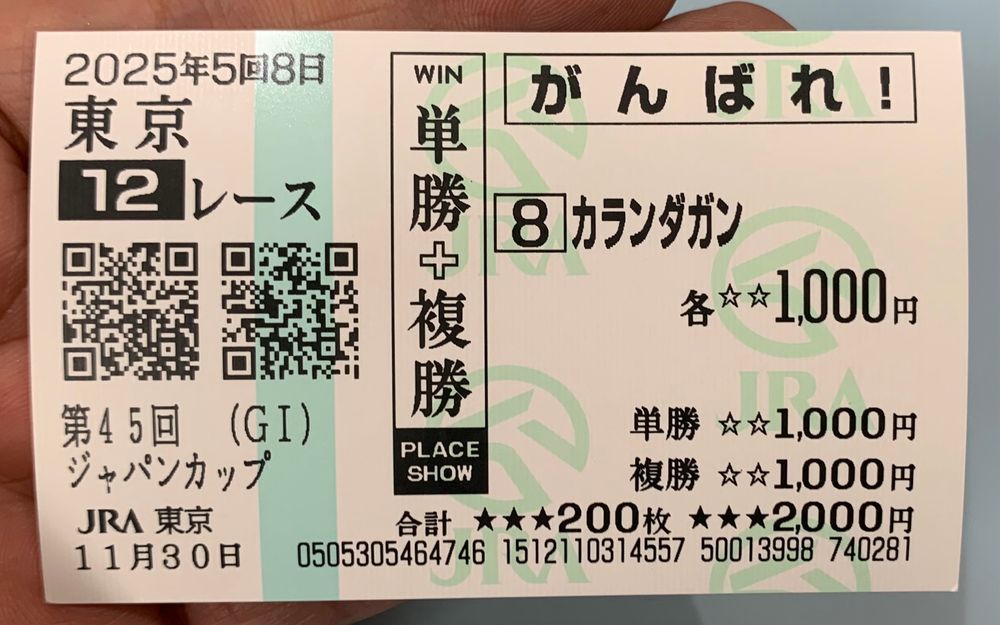
強い!!!!
強い!!!!
なんにせよ、1988年から37年、いろいろあって、今俺んちにこの本はあるわけだ。
本には前の持ち主が買った時のレシートが挟まっていた。電話番号から察するに、埼玉の本屋で買ったらしい。調べたら、どうやらその本屋はもう無い。
なんにせよ、1988年から37年、いろいろあって、今俺んちにこの本はあるわけだ。
本には前の持ち主が買った時のレシートが挟まっていた。電話番号から察するに、埼玉の本屋で買ったらしい。調べたら、どうやらその本屋はもう無い。
本には前の持ち主が買った時のレシートが挟まっていた。電話番号から察するに、埼玉の本屋で買ったらしい。調べたら、どうやらその本屋はもう無い。
騎手デビューの1979年、24歳の音無さんの写真は今の音無さんを若くしたような風体だなあ……と当たり前すぎる感想を抱いた。
騎手デビューの1979年、24歳の音無さんの写真は今の音無さんを若くしたような風体だなあ……と当たり前すぎる感想を抱いた。
騎手デビューの1979年、24歳の音無さんの写真は今の音無さんを若くしたような風体だなあ……と当たり前すぎる感想を抱いた。
痛い痛い気持ちいいマッサージを
してもらって、体中ヘロヘロ!
気持ちよかったわあ♪

痛い痛い気持ちいいマッサージを
してもらって、体中ヘロヘロ!
気持ちよかったわあ♪
でも、ロボット形態のまとめ方は上手いね。
でも、ロボット形態のまとめ方は上手いね。










