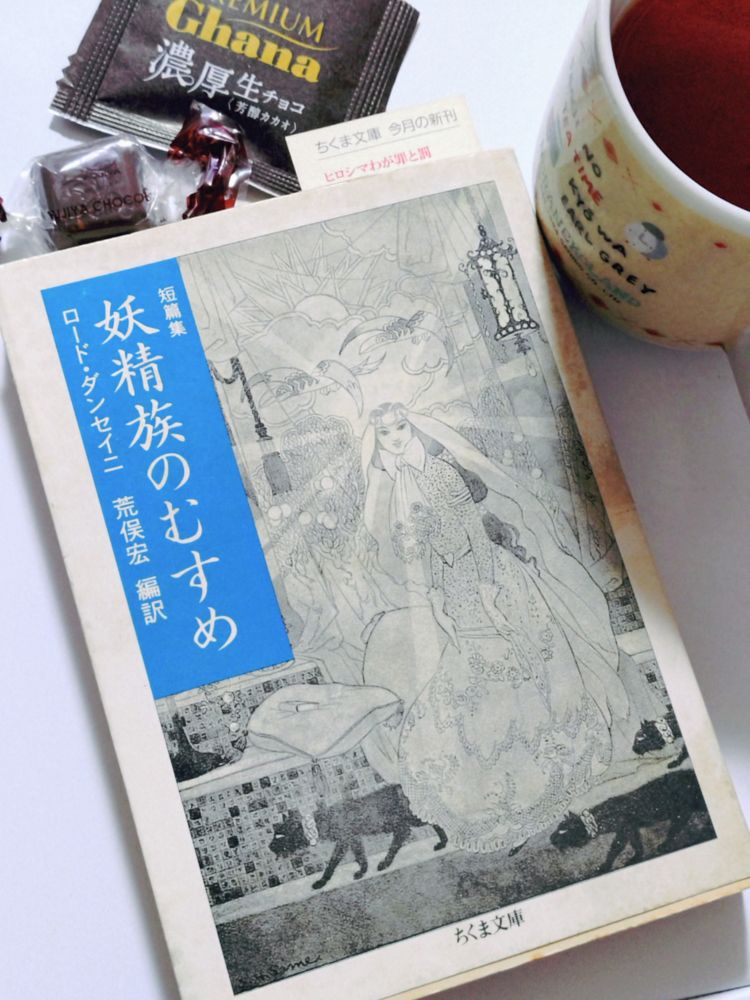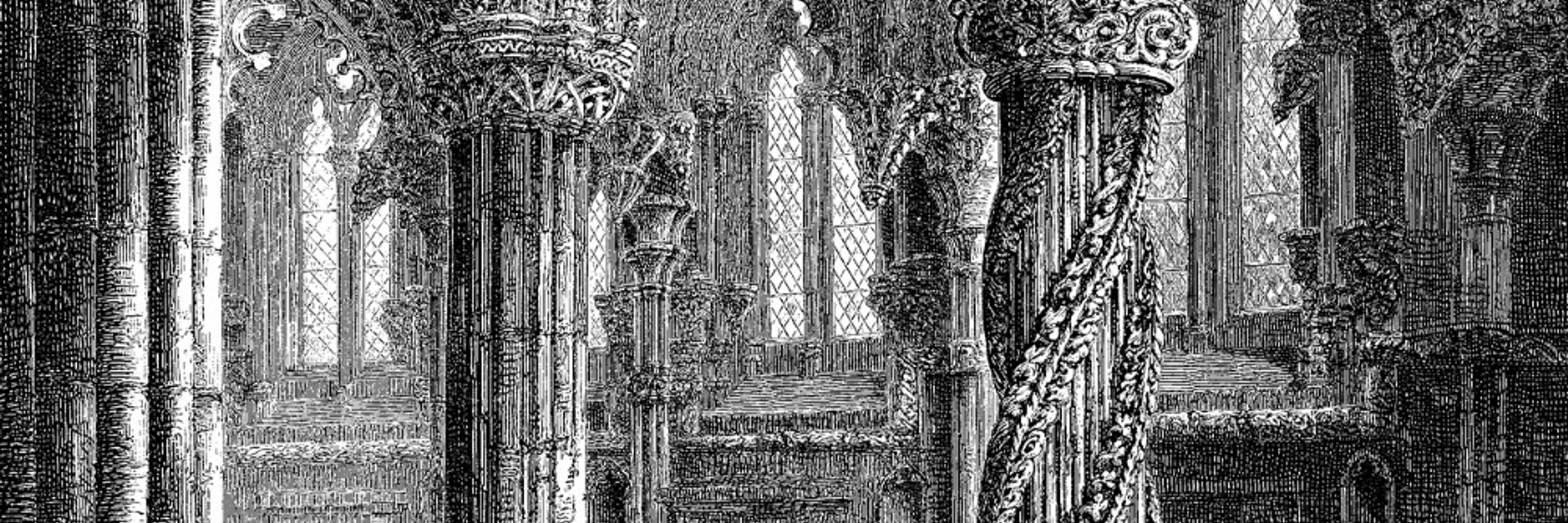
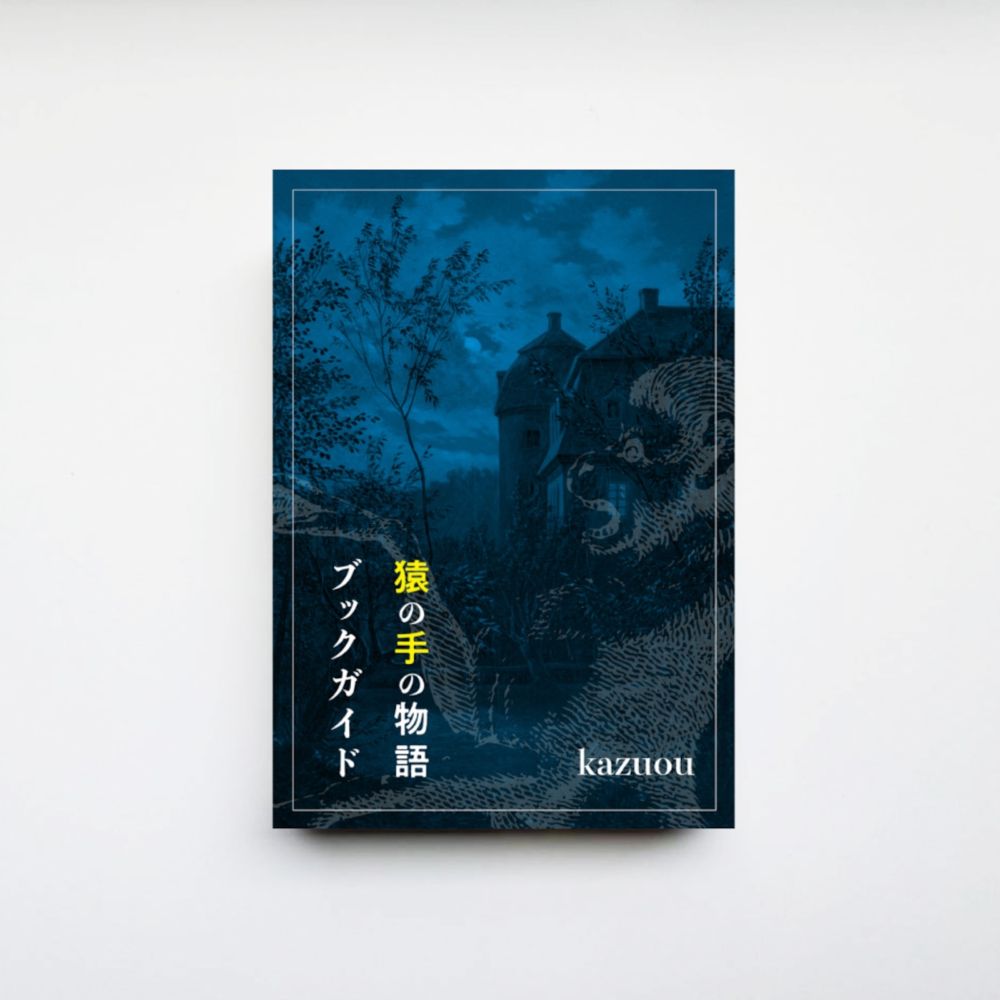
怪奇小説好きには楽しい本だと思います。
サヴァ・ブックスさん
cavabooks.thebase.in/items/106668...
享楽堂さん
www.kyorakudo.jp/product/3354
ブクログの検索機能で、書籍コードを読み取って登録ができるみたいですね。実際やってみました。読み取りのエラーで全然関係ない本が登録されることもたまにあるみたいですが、結構実用的に使えるみたいです。
ちなみに、購入したのはこちらのバーコードリーダー。
www.busicom.co.jp/h/bc-reader/...

ブクログの検索機能で、書籍コードを読み取って登録ができるみたいですね。実際やってみました。読み取りのエラーで全然関係ない本が登録されることもたまにあるみたいですが、結構実用的に使えるみたいです。
ちなみに、購入したのはこちらのバーコードリーダー。
www.busicom.co.jp/h/bc-reader/...
人間の姿で社会に潜み、残虐行為を繰り返す「木人」の殲滅を使命とする女子高生・蘭冷とその僕となった大学生・鈴森一気の活躍を描くホラーシリーズ『フィフス』の続編です。短篇二篇と中篇一篇を収録しています。
「姫と呼ぶ」
若い女性に性的関心を持つ裁縫店の店主・絹川範子は、出入りする学校内で奇矯な言動の美少女・冴羽雪と出会い魅了されます。別の男子生徒との嬌態を見せつける雪に激高した範子は、雪を絞殺してしまいます。死体を森林に遺棄しますが、翌日殺したはずの雪が目の前に現れ、範子は驚愕します…。

人間の姿で社会に潜み、残虐行為を繰り返す「木人」の殲滅を使命とする女子高生・蘭冷とその僕となった大学生・鈴森一気の活躍を描くホラーシリーズ『フィフス』の続編です。短篇二篇と中篇一篇を収録しています。
「姫と呼ぶ」
若い女性に性的関心を持つ裁縫店の店主・絹川範子は、出入りする学校内で奇矯な言動の美少女・冴羽雪と出会い魅了されます。別の男子生徒との嬌態を見せつける雪に激高した範子は、雪を絞殺してしまいます。死体を森林に遺棄しますが、翌日殺したはずの雪が目の前に現れ、範子は驚愕します…。
天使がくれた箱を一生守り続ける男の人生を描いた「天使の箱」、親の留守中に何者かに家を襲われる子供たちの恐怖を描いた「ダフィーのジャケット」、伯父の持つイッカクの角をユニコーンの角と信じてそれを手に入れようとする少年を描いた「ユニコーンの角の指すところ」、

天使がくれた箱を一生守り続ける男の人生を描いた「天使の箱」、親の留守中に何者かに家を襲われる子供たちの恐怖を描いた「ダフィーのジャケット」、伯父の持つイッカクの角をユニコーンの角と信じてそれを手に入れようとする少年を描いた「ユニコーンの角の指すところ」、
キング「呪われた町」を思わせる父子の逃亡劇から始まる。
父が視点人物となる前半では、戦い/逃走している霊媒、教団、〈闇〉の、そして家族の、関連するアルゼンチンの歴史について明らかになっていく。
後半の、何も知らない息子が視点人物になると、多岐にわたる、散りばめられた過去の出来事などから、再構成、発見する(読者は知っている)前半の出来事が明らかにし、また友人らが違う姿を纏って現れ、思わぬ人物が再登場するなど、息もつかせ展開はスリリング。
また、青春小説を思わせるリリカルな逸話、何気ない情景描写やときに不穏さを帯びる描写なども含め読み応えがあった。

キング「呪われた町」を思わせる父子の逃亡劇から始まる。
父が視点人物となる前半では、戦い/逃走している霊媒、教団、〈闇〉の、そして家族の、関連するアルゼンチンの歴史について明らかになっていく。
後半の、何も知らない息子が視点人物になると、多岐にわたる、散りばめられた過去の出来事などから、再構成、発見する(読者は知っている)前半の出来事が明らかにし、また友人らが違う姿を纏って現れ、思わぬ人物が再登場するなど、息もつかせ展開はスリリング。
また、青春小説を思わせるリリカルな逸話、何気ない情景描写やときに不穏さを帯びる描写なども含め読み応えがあった。
以前出た『珈琲と煙草』に近い形式ですが、ただ、エッセイ風味が強かった『珈琲と煙草』に比べて全体に物語性は強いでしょうか。
持ち直した時計工場の社主が脅迫され、脅迫者を突き落としてしまいますが、本当に殺したかは分からない…という「5」、夫が痴漢だと思い込み猜疑心を深める妻が描かれる「8」、

以前出た『珈琲と煙草』に近い形式ですが、ただ、エッセイ風味が強かった『珈琲と煙草』に比べて全体に物語性は強いでしょうか。
持ち直した時計工場の社主が脅迫され、脅迫者を突き落としてしまいますが、本当に殺したかは分からない…という「5」、夫が痴漢だと思い込み猜疑心を深める妻が描かれる「8」、
マンションの一室に住むだけで月給がもらえるという不思議な仕事に就いたタカヒロ。しかしその仕事には条件が一つありました。「隣人」と必ず仲良くしなければならない、というのです。ベランダから気さくに話しかけてくる「隣人」は明らかに人間ではない存在で、しかも彼が話す内容は「怪談」ばかりなのです…。
人間ではない「隣人」と話し続けなければならない、という異様な仕事に就いた青年の日常を描くホラー作品『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』の続編です。

マンションの一室に住むだけで月給がもらえるという不思議な仕事に就いたタカヒロ。しかしその仕事には条件が一つありました。「隣人」と必ず仲良くしなければならない、というのです。ベランダから気さくに話しかけてくる「隣人」は明らかに人間ではない存在で、しかも彼が話す内容は「怪談」ばかりなのです…。
人間ではない「隣人」と話し続けなければならない、という異様な仕事に就いた青年の日常を描くホラー作品『入居条件:隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください』の続編です。
多方面の学位を持ち、あらゆる科学に通じた天才科学者ブルータス・ロイドが難事件に立ち向かうというSFミステリ小説です。
ニューヨークの天才科学者たちが次々と殺されていくという「狙われた天才たち」、寒村で恐竜たちが目撃された事件の真相を探る「意味のない恐竜たち」、原子力研究所で起きた不可解な射殺事件の謎をめぐる「原子世界の弾丸」、事故をきっかけに別世界の情景が見えるようになった技術者を描く「盲目の見者」の四篇を収録しています。
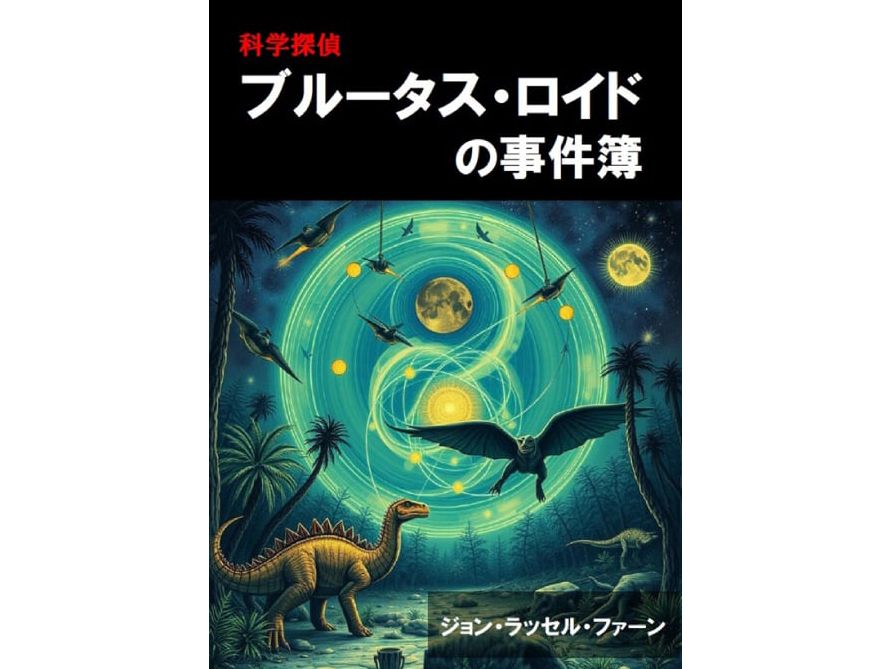
多方面の学位を持ち、あらゆる科学に通じた天才科学者ブルータス・ロイドが難事件に立ち向かうというSFミステリ小説です。
ニューヨークの天才科学者たちが次々と殺されていくという「狙われた天才たち」、寒村で恐竜たちが目撃された事件の真相を探る「意味のない恐竜たち」、原子力研究所で起きた不可解な射殺事件の謎をめぐる「原子世界の弾丸」、事故をきっかけに別世界の情景が見えるようになった技術者を描く「盲目の見者」の四篇を収録しています。
アメリカのユーモア作家ジェームズ・サーバーが、若き日に地元新聞に掲載した連作探偵小説です。名探偵ブルー・プローメルが難事件を解決するミステリ作品なのですが、このプローメルがとんちんかんで思い込みが激しいという性格。推理がことごとく外れたり、それが外れても勢いで何とか片を付けてしまったりと、名探偵というよりは迷探偵といった趣なのです。
アニマルビスケットを愛し、中国人の助手と共に行動します。この中国人助手も片言の英語を話し凡庸に見せながら、その実意外に賢い、というところも笑えます。

アメリカのユーモア作家ジェームズ・サーバーが、若き日に地元新聞に掲載した連作探偵小説です。名探偵ブルー・プローメルが難事件を解決するミステリ作品なのですが、このプローメルがとんちんかんで思い込みが激しいという性格。推理がことごとく外れたり、それが外れても勢いで何とか片を付けてしまったりと、名探偵というよりは迷探偵といった趣なのです。
アニマルビスケットを愛し、中国人の助手と共に行動します。この中国人助手も片言の英語を話し凡庸に見せながら、その実意外に賢い、というところも笑えます。

「悪夢の島」
船乗りのバリーは長年のアルコール中毒によって、日々幻覚に襲われていました。怪物が現れたかと思うと、動物が口を聞くなど、現実と妄想の境がなくなっていたのです。騙されるような形で船に乗ることになりますが、船から落ちた挙げ句、孤島に流れ着きます。そこには触手のような生物が住んでいました。意思疎通が可能な触手生物アニーローは、巨大化した同族を退治してほしいと懇願しますが…。

「悪夢の島」
船乗りのバリーは長年のアルコール中毒によって、日々幻覚に襲われていました。怪物が現れたかと思うと、動物が口を聞くなど、現実と妄想の境がなくなっていたのです。騙されるような形で船に乗ることになりますが、船から落ちた挙げ句、孤島に流れ着きます。そこには触手のような生物が住んでいました。意思疎通が可能な触手生物アニーローは、巨大化した同族を退治してほしいと懇願しますが…。
タイトル通り、エドガー・アラン・ポーの全小説をテーマ別に分類し、簡便な紹介文をつけたガイドです。各作品の紹介も分かりやすくまとめられていて良いのですが、テーマの分類の仕方が楽しいのです。〈厄介な家族/家系の話〉とか<面倒な「友だち」の話>など。「ライジーア」「モレラ」「ベレニス」といった作品群が<愛が歪んでいる人の話>でまとめられているのも面白いですね。

タイトル通り、エドガー・アラン・ポーの全小説をテーマ別に分類し、簡便な紹介文をつけたガイドです。各作品の紹介も分かりやすくまとめられていて良いのですが、テーマの分類の仕方が楽しいのです。〈厄介な家族/家系の話〉とか<面倒な「友だち」の話>など。「ライジーア」「モレラ」「ベレニス」といった作品群が<愛が歪んでいる人の話>でまとめられているのも面白いですね。
ひょんなことから財産を手に入れたビッディヴァ-は、したいことをした結果、虚無感に囚われていました。酒場で飲んだ後、間違った車に乗り込んでしまいますが、それは天才科学者によって作られた最先端の技術を満載した車でした。宇宙にまで上がってしまった車の中で、宇宙線を浴びたビッディヴァ-の体は変異してしまいます…。

ひょんなことから財産を手に入れたビッディヴァ-は、したいことをした結果、虚無感に囚われていました。酒場で飲んだ後、間違った車に乗り込んでしまいますが、それは天才科学者によって作られた最先端の技術を満載した車でした。宇宙にまで上がってしまった車の中で、宇宙線を浴びたビッディヴァ-の体は変異してしまいます…。
フリッツ・フォン・ヘルツマノフスキー=オルランド『フォン・ユブの命取りとなった海への旅』(垂野創一郎訳)は、学者肌の物静かな男アハテイウス・フォン・ユブが旅先で恋に落ち、また羽目を外したことから二進も三進もいかなくなってしまう顛末を描いた作品。女王様然とした歌手の少女のキャラクターが立っています。

フリッツ・フォン・ヘルツマノフスキー=オルランド『フォン・ユブの命取りとなった海への旅』(垂野創一郎訳)は、学者肌の物静かな男アハテイウス・フォン・ユブが旅先で恋に落ち、また羽目を外したことから二進も三進もいかなくなってしまう顛末を描いた作品。女王様然とした歌手の少女のキャラクターが立っています。
主婦の鈴木佳恵は、子供を残して出かけた際に、5歳の娘・芽衣を不運な事故で亡くしてしまいます。悲しみから立ち直れない日々を過ごしますが、骨董市芽衣に似た人形を見つけて衝動的に購入してしまいます。本当の娘のように人形を可愛がりますが、第二子となる娘・真衣を授かり、育てているうちに、人形には目もくれなくなっていました。
5歳になった真衣がひょんなことから人形を見つけ出し、「アヤ」と名付けて一緒に遊ぶようになりますが、それ以来奇妙な出来事が続き、佳恵は人形に原因があるのではと思い至ります…。

主婦の鈴木佳恵は、子供を残して出かけた際に、5歳の娘・芽衣を不運な事故で亡くしてしまいます。悲しみから立ち直れない日々を過ごしますが、骨董市芽衣に似た人形を見つけて衝動的に購入してしまいます。本当の娘のように人形を可愛がりますが、第二子となる娘・真衣を授かり、育てているうちに、人形には目もくれなくなっていました。
5歳になった真衣がひょんなことから人形を見つけ出し、「アヤ」と名付けて一緒に遊ぶようになりますが、それ以来奇妙な出来事が続き、佳恵は人形に原因があるのではと思い至ります…。
ブース数がめちゃくちゃ増えていて、正直全部を見て回るのは無理でした。あらかじめピックアップしていたブースを先に見て回り、そのあとは興味のある分野が固まっている部分を集中的に見る…という感じでしょうか。
ブースも人も増えてはいるのですが、それ以上に会場が広くなったので、旧会場(東京流通センター)の時よりは、通路の移動は楽になっているなと感じました。




ブース数がめちゃくちゃ増えていて、正直全部を見て回るのは無理でした。あらかじめピックアップしていたブースを先に見て回り、そのあとは興味のある分野が固まっている部分を集中的に見る…という感じでしょうか。
ブースも人も増えてはいるのですが、それ以上に会場が広くなったので、旧会場(東京流通センター)の時よりは、通路の移動は楽になっているなと感じました。
無名の新人作家の「私」のもとに舞い込んだのは、とあるアイドルグループの行方調査依頼でした。そのグループ「メランコリック・フルール」は一年半の活動の後、ステージ上で流血沙汰が起き、解散してしまったといいます。メンバー四人の行方も分かりません。「メンバーの中に人殺しがいる」という噂もありました。
次回作の企画に悩んでいた「私」は、アイドルたちを次の本の主題にすることとし、ささいな手がかりからメンバーそれぞれの行方を追っていくことになりますが…。

無名の新人作家の「私」のもとに舞い込んだのは、とあるアイドルグループの行方調査依頼でした。そのグループ「メランコリック・フルール」は一年半の活動の後、ステージ上で流血沙汰が起き、解散してしまったといいます。メンバー四人の行方も分かりません。「メンバーの中に人殺しがいる」という噂もありました。
次回作の企画に悩んでいた「私」は、アイドルたちを次の本の主題にすることとし、ささいな手がかりからメンバーそれぞれの行方を追っていくことになりますが…。
前作同様、奇怪なバイト内容について語られる連作ホラー集となっています。高齢者に勉強を教える家庭教師のバイト、部屋の電気をつけるだけの仕事、特定の場所での写真撮影のバイト、遭難者の遺体を探すバイト、バスに乗って降りる行為を繰り返すバイトなどの内容が語られます。
行う行為の理由が分からない不気味なバイトの他にも、目的がはっきりしているように見えるバイトも、やっている内にその不可解さが実感されてくる…というところが怖いですね。

前作同様、奇怪なバイト内容について語られる連作ホラー集となっています。高齢者に勉強を教える家庭教師のバイト、部屋の電気をつけるだけの仕事、特定の場所での写真撮影のバイト、遭難者の遺体を探すバイト、バスに乗って降りる行為を繰り返すバイトなどの内容が語られます。
行う行為の理由が分からない不気味なバイトの他にも、目的がはっきりしているように見えるバイトも、やっている内にその不可解さが実感されてくる…というところが怖いですね。
タニス・リーの<パラディスの秘録>シリーズ全四作を紹介しています。退廃と背徳の都パラディスを舞台にした怪奇幻想小説のシリーズです。
kimyo.blog50.fc2.com/blog-entry-2...

タニス・リーの<パラディスの秘録>シリーズ全四作を紹介しています。退廃と背徳の都パラディスを舞台にした怪奇幻想小説のシリーズです。
kimyo.blog50.fc2.com/blog-entry-2...
変わり者の探偵・四里川陣とその助手の四ッ谷礼子は、ある日老婦人の訪問を受けます。その婦人仁科順子は、嫁が殺された事件をめぐって息子の達彦の容疑を晴らしてほしいというのです。四里川に命じられて、礼子は雪山に建つホテルで起こった殺人事件の調査に赴くことになります。
被害者の浬奈は密室の外で死んでいました。警察によれば殺人とも自殺とも訳の分からない状態だというのです。容疑者は夫の達彦の他、その愛人の新藤礼都、顧問弁護士の西条源治でした。礼子は容疑者たちから地道に聞き取りを行うことになりますが…。

変わり者の探偵・四里川陣とその助手の四ッ谷礼子は、ある日老婦人の訪問を受けます。その婦人仁科順子は、嫁が殺された事件をめぐって息子の達彦の容疑を晴らしてほしいというのです。四里川に命じられて、礼子は雪山に建つホテルで起こった殺人事件の調査に赴くことになります。
被害者の浬奈は密室の外で死んでいました。警察によれば殺人とも自殺とも訳の分からない状態だというのです。容疑者は夫の達彦の他、その愛人の新藤礼都、顧問弁護士の西条源治でした。礼子は容疑者たちから地道に聞き取りを行うことになりますが…。
ヘラジカを追ってカナダの原始林に足を踏み入れた一行を待ち受ける未知の恐怖体験。はたして伝説の獣、ウェンディゴとは一体なんなのか。
相変わらず雄大な自然描写が素晴らしい。森林のひんやりとした温度や匂いまで感じるような文章は流石。
ウェンディゴの正体や描写は仄めかされるだけではっきりと具体的には語られていないもののそれが却って想像力を刺激して恐ろしいものに仕立てている。ウェンディゴに連れ去られてしまったかと思われたディファーゴが戻ってきたシーンは安堵したのも束の間。廃人のようになってしまった彼に一体何があったのか判らないところも恐怖心を掻き立てられる

ヘラジカを追ってカナダの原始林に足を踏み入れた一行を待ち受ける未知の恐怖体験。はたして伝説の獣、ウェンディゴとは一体なんなのか。
相変わらず雄大な自然描写が素晴らしい。森林のひんやりとした温度や匂いまで感じるような文章は流石。
ウェンディゴの正体や描写は仄めかされるだけではっきりと具体的には語られていないもののそれが却って想像力を刺激して恐ろしいものに仕立てている。ウェンディゴに連れ去られてしまったかと思われたディファーゴが戻ってきたシーンは安堵したのも束の間。廃人のようになってしまった彼に一体何があったのか判らないところも恐怖心を掻き立てられる
パラディスだけでなく、その並行世界の都市パラダイス、そしてパラディと、三つの都市の物語が同時に展開するというSF的な要素の強いファンタジー作品です。時代も現代に近いこともあり、シリーズの他の作品とは毛色が異なっていますね。
パラダイスでは、日々殺人を繰り返す双子の兄妹フェリオンとスマラ、パラディスでは、俳優に憧れた挙げ句、精神病院に収容されてしまう15歳の少女イルド、パラディでは、恋人殺害の冤罪をかけられ狂人扱いされてしまう画家の女性レオカディアが登場します。

パラディスだけでなく、その並行世界の都市パラダイス、そしてパラディと、三つの都市の物語が同時に展開するというSF的な要素の強いファンタジー作品です。時代も現代に近いこともあり、シリーズの他の作品とは毛色が異なっていますね。
パラダイスでは、日々殺人を繰り返す双子の兄妹フェリオンとスマラ、パラディスでは、俳優に憧れた挙げ句、精神病院に収容されてしまう15歳の少女イルド、パラディでは、恋人殺害の冤罪をかけられ狂人扱いされてしまう画家の女性レオカディアが登場します。
「鼬の花嫁」
子供のころから愛し合い、結婚することになったロランとマリー。しかし貞淑で美しいマリーをロランは婚礼の日に絞殺してしまいます。裁判にかけられても、殺害の理由を話さぬままロランは処刑されてしまいます。死の直前の書置きが司祭に送られるものの、司祭もまたその秘密を秘匿してしまいます…。
純真な少女が隠していた秘密とは何なのか? 少女が思われていたほど純真ではなかったことが途中から判明するものの、

「鼬の花嫁」
子供のころから愛し合い、結婚することになったロランとマリー。しかし貞淑で美しいマリーをロランは婚礼の日に絞殺してしまいます。裁判にかけられても、殺害の理由を話さぬままロランは処刑されてしまいます。死の直前の書置きが司祭に送られるものの、司祭もまたその秘密を秘匿してしまいます…。
純真な少女が隠していた秘密とは何なのか? 少女が思われていたほど純真ではなかったことが途中から判明するものの、