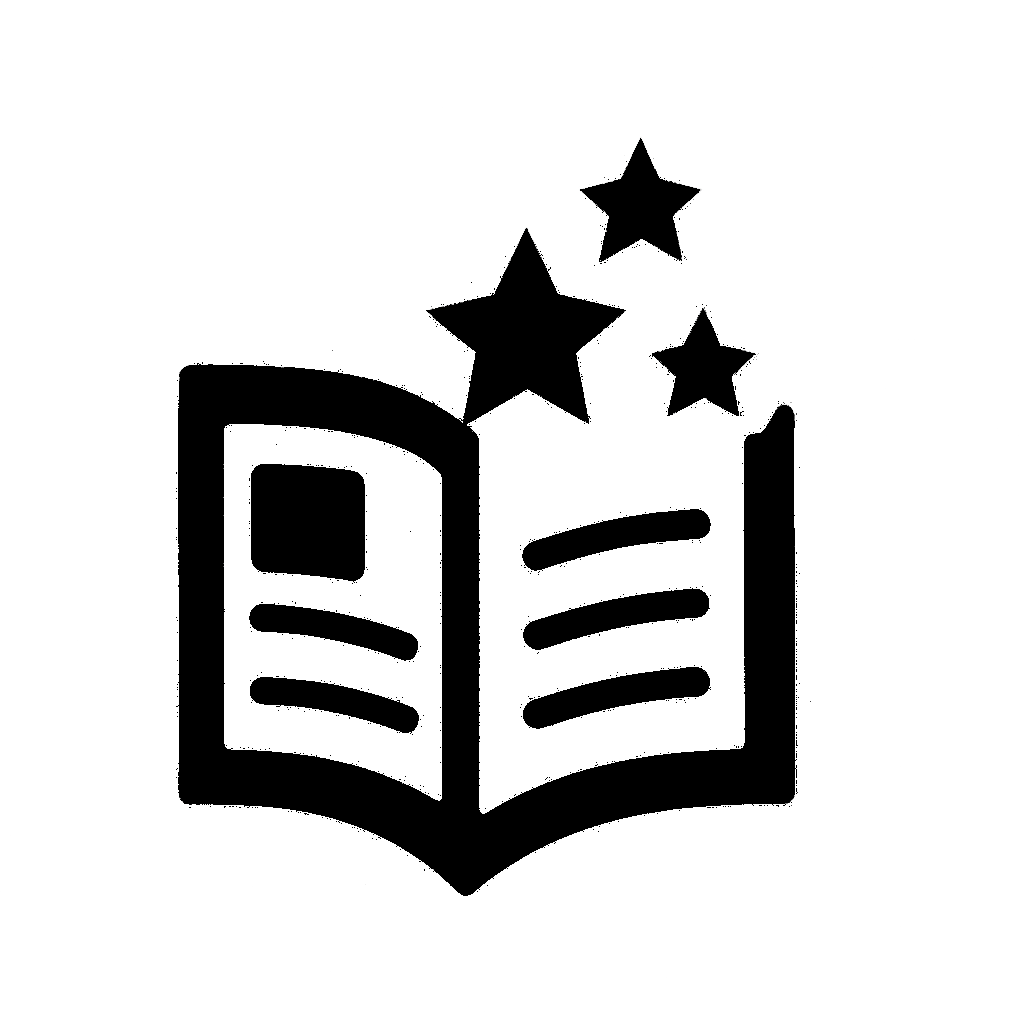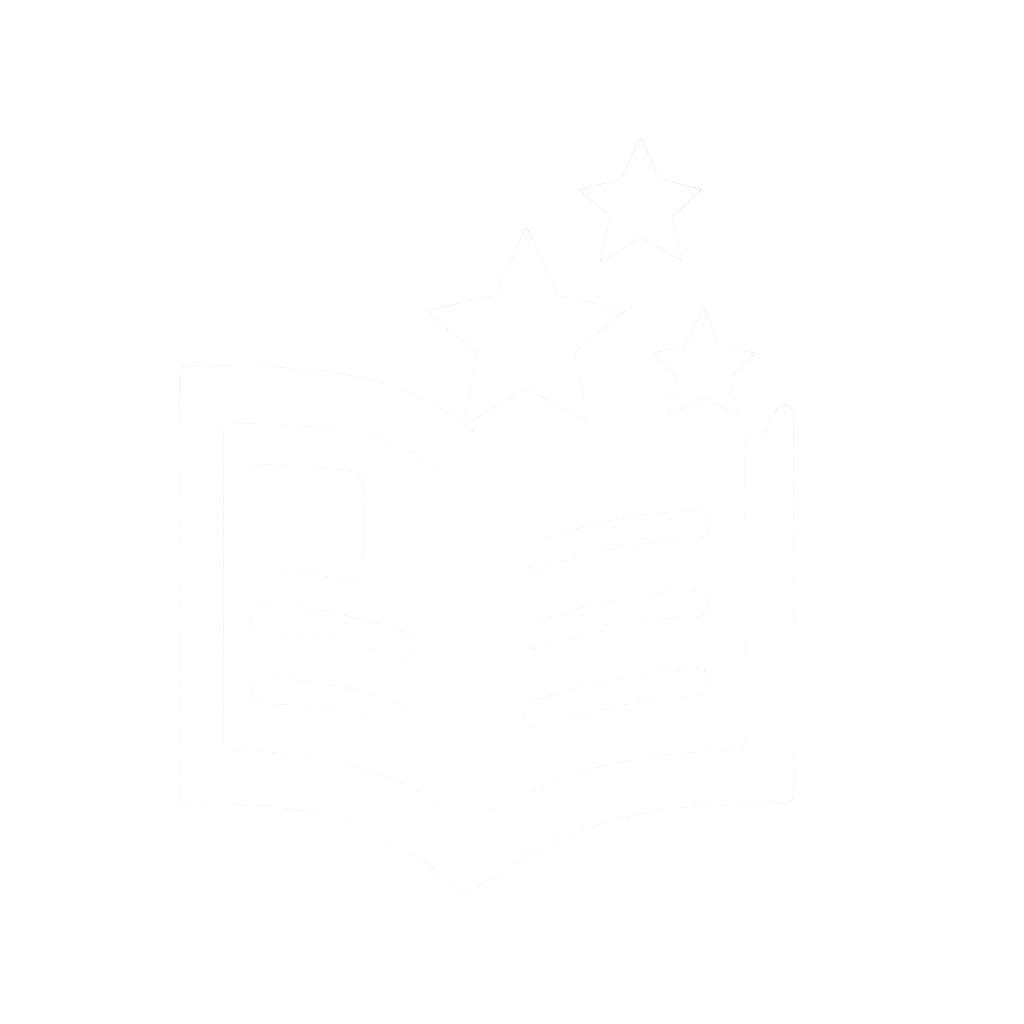あ
@a3dayo.bsky.social
58 followers
84 following
540 posts
Early modern military history lover, tercio big lover.
My blog: https://a3dayo.hatenablog.com/
Fedibird: https://fedibird.com/@a3dayo
Fediverse: @[email protected]
Posts
Media
Videos
Starter Packs
あ
@a3dayo.bsky.social
· 1d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 2d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 3d
Reposted by あ
Reposted by あ
『着物になった〈戦争〉』、戦中の戦争柄着物がペラペラだというおはなし、そうか銘仙か!
戦中華美な服装は忌むべきものとされたが戦争柄は許された。戦争柄を着た若い女性たちは決してハーケンクロイツや旭日旗を着たかったわけではなく鮮やかな着物が着たかったのだろう。しかしその戦争柄を受容する土壌は確かに社会に影響を与えていた…
戦中華美な服装は忌むべきものとされたが戦争柄は許された。戦争柄を着た若い女性たちは決してハーケンクロイツや旭日旗を着たかったわけではなく鮮やかな着物が着たかったのだろう。しかしその戦争柄を受容する土壌は確かに社会に影響を与えていた…
Reposted by あ
Reposted by あ
Reposted by あ
Reposted by あ
Reposted by あ
Reposted by あ
あ
@a3dayo.bsky.social
· 6d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 9d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 11d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 11d
あ
@a3dayo.bsky.social
· 13d