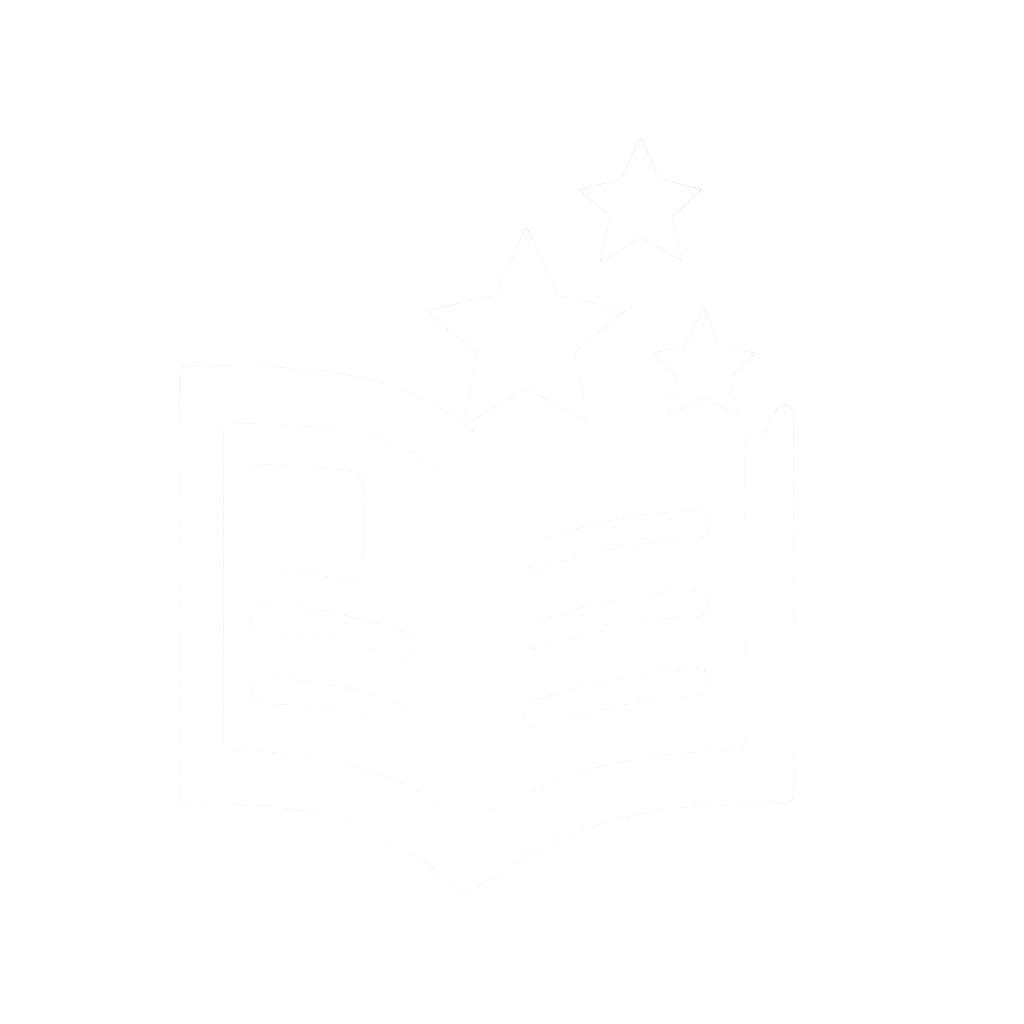Mitsutaka Nagira
@elisragina.bsky.social
1.6K followers
96 following
1.4K posts
島根県出雲市出身。ライター、DJ、ラジオ・パーソナリティ、エデュケーター。JTNCの中の人です
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Reposted by Mitsutaka Nagira
tt
@tt51970410.bsky.social
· 17h
Reposted by Mitsutaka Nagira
Reposted by Mitsutaka Nagira