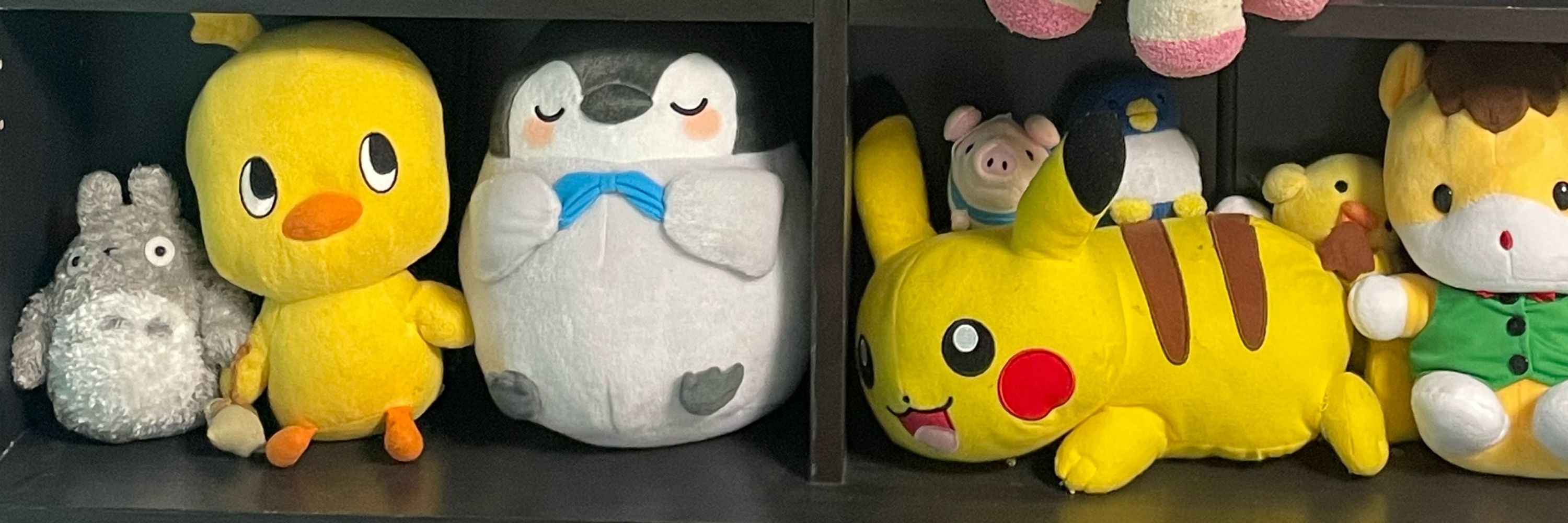
アジール論は重層的権力という特徴を持つ中世史研究に多いと思われる(誤っていたら済まない)のだが、近世史研究に適用するというのは美点だと思われる。近世という独自の時代――決して主権国家のアリーナとなっていく近代の初期ではない――を分析するという西洋近世史研究とどれほと日本近世史研究が志向を共にしているのか分からないけれども、日本近世史の地平を拡げる研究になりそうだ。
November 11, 2025 at 6:47 AM
アジール論は重層的権力という特徴を持つ中世史研究に多いと思われる(誤っていたら済まない)のだが、近世史研究に適用するというのは美点だと思われる。近世という独自の時代――決して主権国家のアリーナとなっていく近代の初期ではない――を分析するという西洋近世史研究とどれほと日本近世史研究が志向を共にしているのか分からないけれども、日本近世史の地平を拡げる研究になりそうだ。
那須野が色々と強烈過ぎて高宮を覚えていなかったという言い訳を述べておく(君の方がTBS時代を理解している)。
November 6, 2025 at 6:19 AM
那須野が色々と強烈過ぎて高宮を覚えていなかったという言い訳を述べておく(君の方がTBS時代を理解している)。
・美点としては、史料批判と実社会の生活とを結びつけた点。史料からの情報を扱う学問たる歴史学は、情報化社会にとって必要な能力を養うことになると言える。このような歴史を学ぶ現代的意義について、歴史教育の理念の面ではつとに指摘されている(例えば、学習指導要領における「主体的・ 対話的で深い学び」)。この点が掘り下げられていたのならば、氏の議論に拡がりが生まれたであろう。
・歴史学、ひいては人文科学が直面している現実を考えなければならないという問題意識それ自体には共感する。
・歴史学、ひいては人文科学が直面している現実を考えなければならないという問題意識それ自体には共感する。
November 5, 2025 at 11:18 AM
・美点としては、史料批判と実社会の生活とを結びつけた点。史料からの情報を扱う学問たる歴史学は、情報化社会にとって必要な能力を養うことになると言える。このような歴史を学ぶ現代的意義について、歴史教育の理念の面ではつとに指摘されている(例えば、学習指導要領における「主体的・ 対話的で深い学び」)。この点が掘り下げられていたのならば、氏の議論に拡がりが生まれたであろう。
・歴史学、ひいては人文科学が直面している現実を考えなければならないという問題意識それ自体には共感する。
・歴史学、ひいては人文科学が直面している現実を考えなければならないという問題意識それ自体には共感する。
郭源治だね。無関係だが西武には郭泰源がいた。
October 26, 2025 at 4:12 PM
郭源治だね。無関係だが西武には郭泰源がいた。
某法学部図書館でそのルール知って、???の気持ちだった。まあ分からなくはないが。
September 26, 2025 at 9:43 AM
某法学部図書館でそのルール知って、???の気持ちだった。まあ分からなくはないが。

