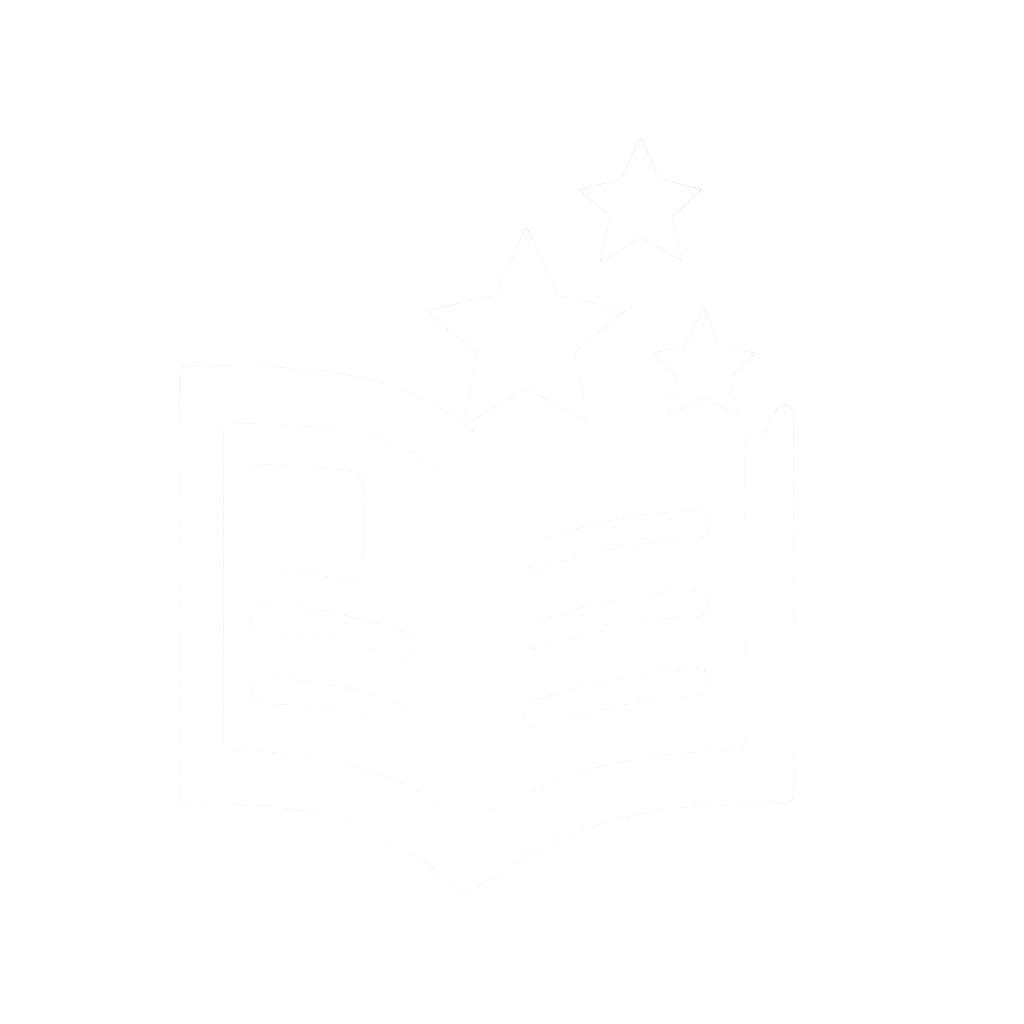渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
110 followers
76 following
450 posts
英国とアイルランドの怪奇幻想小説が好きな翻訳家。アルジャナン・ブラックウッド全訳計画を進めています。
【最近の翻訳】
アルジャーノン・ブラックウッド「木に愛された男」(『新編怪奇幻想の文学3』所収)、「五月祭前夜」(同『4』所収)、「古い衣」(同『5』所収)、「ジョーンズの狂気」(『幻想と怪奇15』所収)
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
Reposted by 渦巻栗
中野善夫
@tolleetlege.bsky.social
· 20h
渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
· 10d
渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
· 10d
渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
· 10d
渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
· 11d
渦巻栗
@uzumakikuri.bsky.social
· 11d
Reposted by 渦巻栗