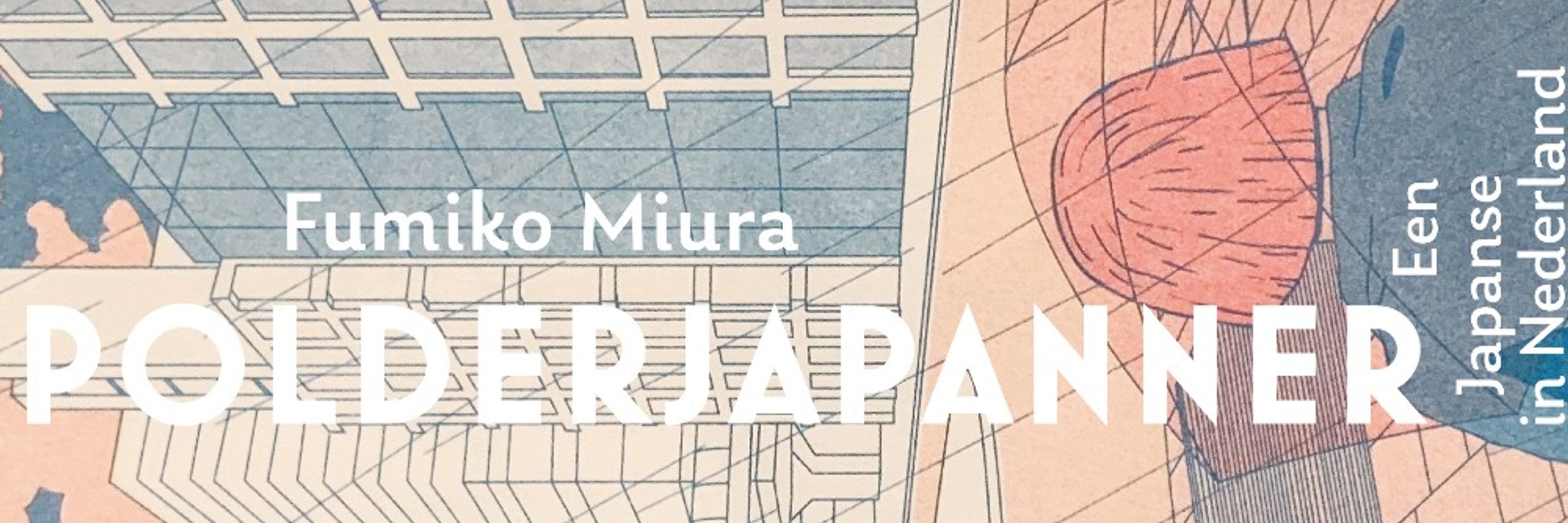
Auteur 'Polderjapanner' (2023) Uitgeverij Van Oorschot
https://www.vanoorschot.nl/writers/fumiko-miura/
Rotterdam, The Netherlands
たった4秒のシーンを作るのに約1年以上もかけたとか、朝9時から朝5時まで働いていた、とか。
それを読んだオランダ人の若者はおかしいって呆れてたけど、私もこういうエピソードを自慢げに教科書に入れ込んでくるジャパンタイムズの編集部、何考えてんのかな、と思うよ。
じゃあそんな教科書使わなければいいのだろうが…。
たった4秒のシーンを作るのに約1年以上もかけたとか、朝9時から朝5時まで働いていた、とか。
それを読んだオランダ人の若者はおかしいって呆れてたけど、私もこういうエピソードを自慢げに教科書に入れ込んでくるジャパンタイムズの編集部、何考えてんのかな、と思うよ。
じゃあそんな教科書使わなければいいのだろうが…。
「もしドッペッてみろ」
って一瞬なんのことだか分からなかったけど、ダブる=留年 することか。
なんでアルバイトは現代まで残って、ドッペるは残らなかったんだろう🤔
難しい言葉も多いし、農民が困窮極まるなか、軍国主義がますます幅をきかせ言論弾圧が強まる昭和初期、新興宗教にも弾圧の手が伸びるという、読んでいても重苦しく決して楽しくない小説ではあるけど、あの時代の空気を知るためにも読んでおきたいのでかじりついている。
うちの婆さん兄弟も同じ時期に天理教にはまっていたので、全く関係のない話とは思えないんだよね。どうして婆さんたちがあんなに天理教に熱心だったのか、これを読んだらちょっと理解できるかも。
その反動で、うちの母は新興宗教を憎悪するようになったのだけど。

「もしドッペッてみろ」
って一瞬なんのことだか分からなかったけど、ダブる=留年 することか。
なんでアルバイトは現代まで残って、ドッペるは残らなかったんだろう🤔

きーんし輝く日本の
あいこでアメリカ ヨーロッパ
パパパラリの 新学期
にんにん肉屋の 大泥棒
ああ青春の 鐘が鳴ります
キンコンカン
の
きんし輝く日本の
の部分って、紀元二千六百年の歌だったって今知った!
きーんし輝く日本の
あいこでアメリカ ヨーロッパ
パパパラリの 新学期
にんにん肉屋の 大泥棒
ああ青春の 鐘が鳴ります
キンコンカン
の
きんし輝く日本の
の部分って、紀元二千六百年の歌だったって今知った!
こういう人は違うことを前提とした主権者教育、日本でも真剣に取り組めるといい。
道徳や公民が目指していたものだったかもしれないが、どうしても全体の規律の方を優先してしまう学校という場がいけないのか。みんなちがってみんないい、と詩を読ませるだけで実現できるようなものでもない。
www.asahi.com/withplanet/a...

こういう人は違うことを前提とした主権者教育、日本でも真剣に取り組めるといい。
道徳や公民が目指していたものだったかもしれないが、どうしても全体の規律の方を優先してしまう学校という場がいけないのか。みんなちがってみんないい、と詩を読ませるだけで実現できるようなものでもない。
www.asahi.com/withplanet/a...
難しい言葉も多いし、農民が困窮極まるなか、軍国主義がますます幅をきかせ言論弾圧が強まる昭和初期、新興宗教にも弾圧の手が伸びるという、読んでいても重苦しく決して楽しくない小説ではあるけど、あの時代の空気を知るためにも読んでおきたいのでかじりついている。
うちの婆さん兄弟も同じ時期に天理教にはまっていたので、全く関係のない話とは思えないんだよね。どうして婆さんたちがあんなに天理教に熱心だったのか、これを読んだらちょっと理解できるかも。
その反動で、うちの母は新興宗教を憎悪するようになったのだけど。

難しい言葉も多いし、農民が困窮極まるなか、軍国主義がますます幅をきかせ言論弾圧が強まる昭和初期、新興宗教にも弾圧の手が伸びるという、読んでいても重苦しく決して楽しくない小説ではあるけど、あの時代の空気を知るためにも読んでおきたいのでかじりついている。
うちの婆さん兄弟も同じ時期に天理教にはまっていたので、全く関係のない話とは思えないんだよね。どうして婆さんたちがあんなに天理教に熱心だったのか、これを読んだらちょっと理解できるかも。
その反動で、うちの母は新興宗教を憎悪するようになったのだけど。

難しい言葉も多いし、農民が困窮極まるなか、軍国主義がますます幅をきかせ言論弾圧が強まる昭和初期、新興宗教にも弾圧の手が伸びるという、読んでいても重苦しく決して楽しくない小説ではあるけど、あの時代の空気を知るためにも読んでおきたいのでかじりついている。
うちの婆さん兄弟も同じ時期に天理教にはまっていたので、全く関係のない話とは思えないんだよね。どうして婆さんたちがあんなに天理教に熱心だったのか、これを読んだらちょっと理解できるかも。
その反動で、うちの母は新興宗教を憎悪するようになったのだけど。
でもここ数年、まったく更新が無くて、どうなさったのかと遠巻きに心配している😥
www.instagram.com/woolensocks_...
でもここ数年、まったく更新が無くて、どうなさったのかと遠巻きに心配している😥
www.instagram.com/woolensocks_...
オランダ、カナダとNHKの共同制作のようで、実際の戦後の風景や極東国際軍事裁判の映像(恐らくNHK提供)や、今は明治村にあるフランク・ロイド・ライト設計の帝国ホテルの建物が使われていた。
詳細については私はほとんど知らないので、どこまで史実に基づいているか知らないけど、連合国11か国を代表する法律家のそれぞれの見識や思惑が見えて興味深かった。
インドやフィリピンなど西洋諸国にずっと植民地支配されてきた国の裁判官が、オランダが終戦後にインドネシアを再植民地化しようと派兵していたことに
www.netflix.com/nl/title/800...

オランダ、カナダとNHKの共同制作のようで、実際の戦後の風景や極東国際軍事裁判の映像(恐らくNHK提供)や、今は明治村にあるフランク・ロイド・ライト設計の帝国ホテルの建物が使われていた。
詳細については私はほとんど知らないので、どこまで史実に基づいているか知らないけど、連合国11か国を代表する法律家のそれぞれの見識や思惑が見えて興味深かった。
インドやフィリピンなど西洋諸国にずっと植民地支配されてきた国の裁判官が、オランダが終戦後にインドネシアを再植民地化しようと派兵していたことに
www.netflix.com/nl/title/800...
めちゃめちゃ面白くて夢中で読みました。『百年の孤独』を意識しているようですが、まさにインドネシアの百年の孤独。ガルシア・マルケスが好きな人は絶対好きだと思う。
後で感想を書きます。
いい本を読んだ。 #読了

めちゃめちゃ面白くて夢中で読みました。『百年の孤独』を意識しているようですが、まさにインドネシアの百年の孤独。ガルシア・マルケスが好きな人は絶対好きだと思う。
後で感想を書きます。
いい本を読んだ。 #読了
本を読みながら編むのか、編みながら本を読むのか、どっちがメインか?と尋ねられると自分でも分からないのだが、読むだけだと手持ち無沙汰で、何も凝った柄物のセーターを作ろうとは考えてないので、自分は読むがメインなのかな。
私は翻訳者の斉藤真理子さんのエッセイを読んでから、私は本格的に読みながら編む人になりました。
橋本治さんは読みながら複雑な柄物を編んでいたマルチタスクの猛者だったそうです。

本を読みながら編むのか、編みながら本を読むのか、どっちがメインか?と尋ねられると自分でも分からないのだが、読むだけだと手持ち無沙汰で、何も凝った柄物のセーターを作ろうとは考えてないので、自分は読むがメインなのかな。
私は翻訳者の斉藤真理子さんのエッセイを読んでから、私は本格的に読みながら編む人になりました。
橋本治さんは読みながら複雑な柄物を編んでいたマルチタスクの猛者だったそうです。
オランダ移住は上手く行っている家族はいいけど、こういうこともあるから安易に勧められるものでもないよ。
とにかく日本を出たい人の耳には何を言っても届かないけどさ。
オランダ移住は上手く行っている家族はいいけど、こういうこともあるから安易に勧められるものでもないよ。
とにかく日本を出たい人の耳には何を言っても届かないけどさ。
マンモとエコー検診とお医者さんと10分の面談で515ユーロか...かける180円しちゃだめだ。
だからオランダではみんな検診行きたがらないんだよね。
マンモとエコー検診とお医者さんと10分の面談で515ユーロか...かける180円しちゃだめだ。
だからオランダではみんな検診行きたがらないんだよね。
普通に美味しいレストランがあったら、日本人は食べログで★3つを付けるところを、オランダ人は同じレストランにGoogle Mapで★5つを付ける、ぐらいに考えておいた方がいいのでは。
普通に美味しいレストランがあったら、日本人は食べログで★3つを付けるところを、オランダ人は同じレストランにGoogle Mapで★5つを付ける、ぐらいに考えておいた方がいいのでは。
オランダ語なんて自分も間違えまくってるから、私はよう教えられないわ。
文法の骨組みだけ教えればしゃべれるようになる言語じゃないし、成人になってから習得した人は、大概発音にくせがあるから。
あれかな、日本は英語教師でも英語しゃべれなかったりするから、教師自身がそれほど目標言語ができなくても免疫があるからかしら。
日本語教師界隈で、ネイティブ教師信奉の是非みたいな話題が時々あがるけど、自分がオランダ語習うなら絶対ネイティブがいいわ。
オランダ語なんて自分も間違えまくってるから、私はよう教えられないわ。
文法の骨組みだけ教えればしゃべれるようになる言語じゃないし、成人になってから習得した人は、大概発音にくせがあるから。
あれかな、日本は英語教師でも英語しゃべれなかったりするから、教師自身がそれほど目標言語ができなくても免疫があるからかしら。
日本語教師界隈で、ネイティブ教師信奉の是非みたいな話題が時々あがるけど、自分がオランダ語習うなら絶対ネイティブがいいわ。
日本でもヘビメタ生活を楽しんでいる模様。
日本のヘビメタ界隈の皆様、モサモサ白髪の身長188cmオランダ人を見つけたら仲良くしてやって下さい🙇♀️ よろしくお願いします。
日本でもヘビメタ生活を楽しんでいる模様。
日本のヘビメタ界隈の皆様、モサモサ白髪の身長188cmオランダ人を見つけたら仲良くしてやって下さい🙇♀️ よろしくお願いします。
学校でしかお習字をしないと、墨はボトルに入っている物、という理解なんだな。
一昨年奈良で墨作り体験に行ったので、墨の材料や作り方が説明できてよかった。
学校でしかお習字をしないと、墨はボトルに入っている物、という理解なんだな。
一昨年奈良で墨作り体験に行ったので、墨の材料や作り方が説明できてよかった。
www.hisaizujinja.jp
www.hisaizujinja.jp
もちろんその頃にはフェイエノールトのサッカー場は無く、製鉄所を視察に来たそうですが😆
オランダに来た時に至るところで熱烈歓迎されている様子が伝わってくる(前寄港地のイギリスではそれほどの歓迎ぶりではなかったようなので余計に)。野次馬の凄まじさも記録されている。
そりゃ19世紀のオランダにいきなりサムライたちが現れたら、一目見てみたいよね。その気持ちはめっちゃ分かる。


もちろんその頃にはフェイエノールトのサッカー場は無く、製鉄所を視察に来たそうですが😆
オランダに来た時に至るところで熱烈歓迎されている様子が伝わってくる(前寄港地のイギリスではそれほどの歓迎ぶりではなかったようなので余計に)。野次馬の凄まじさも記録されている。
そりゃ19世紀のオランダにいきなりサムライたちが現れたら、一目見てみたいよね。その気持ちはめっちゃ分かる。






