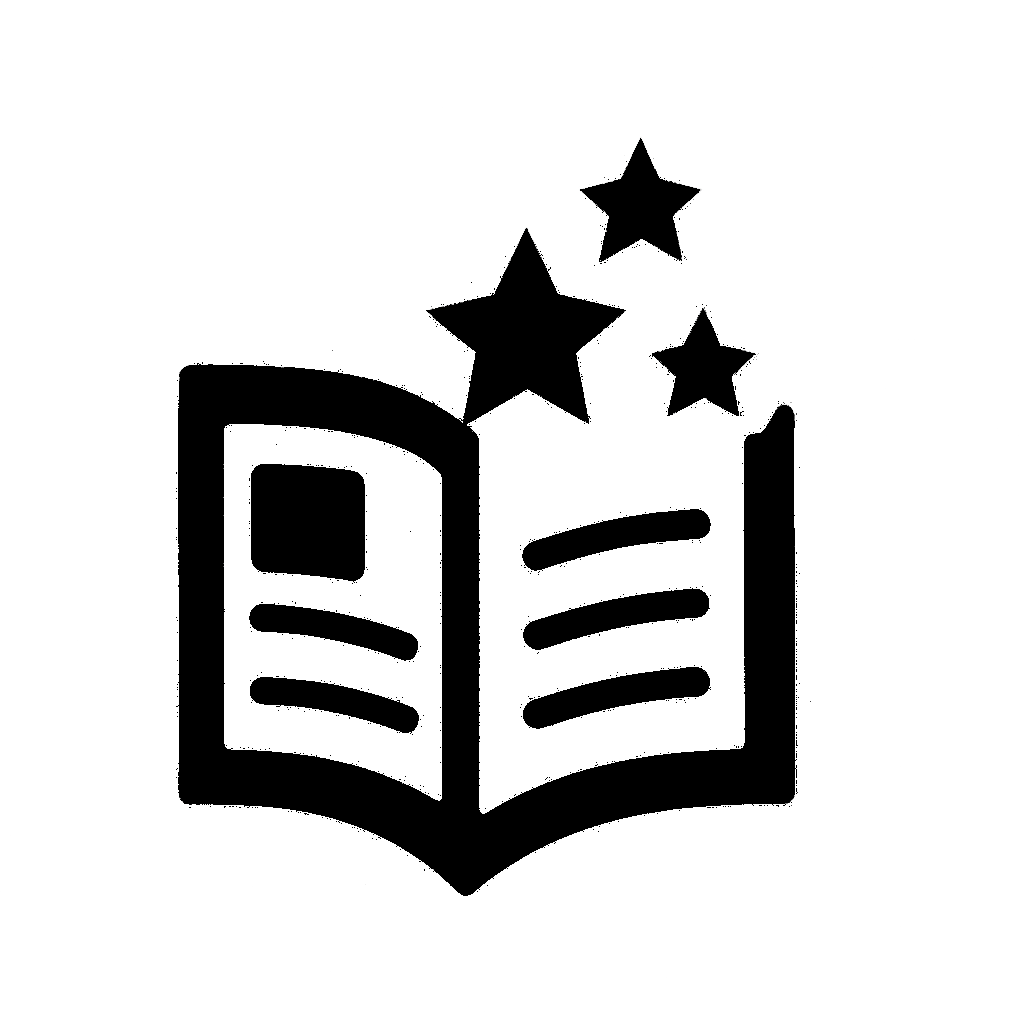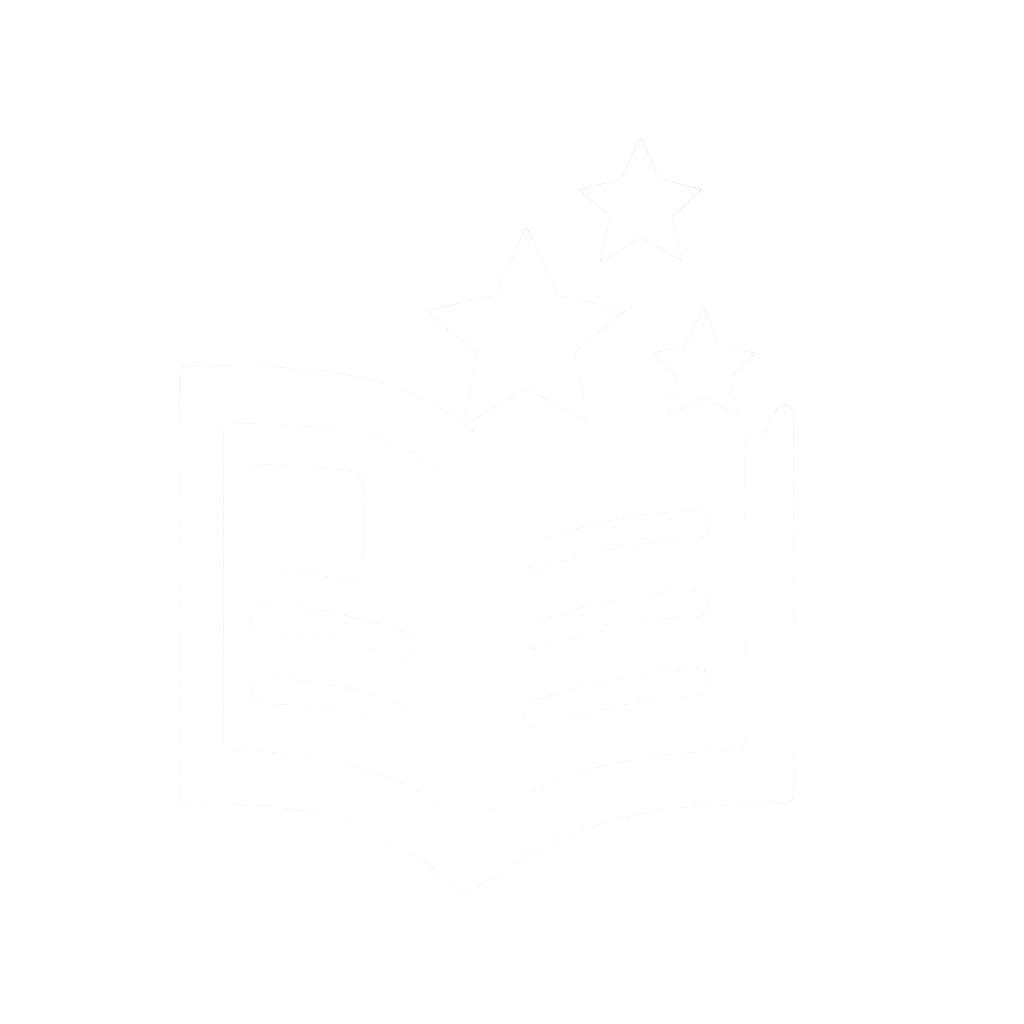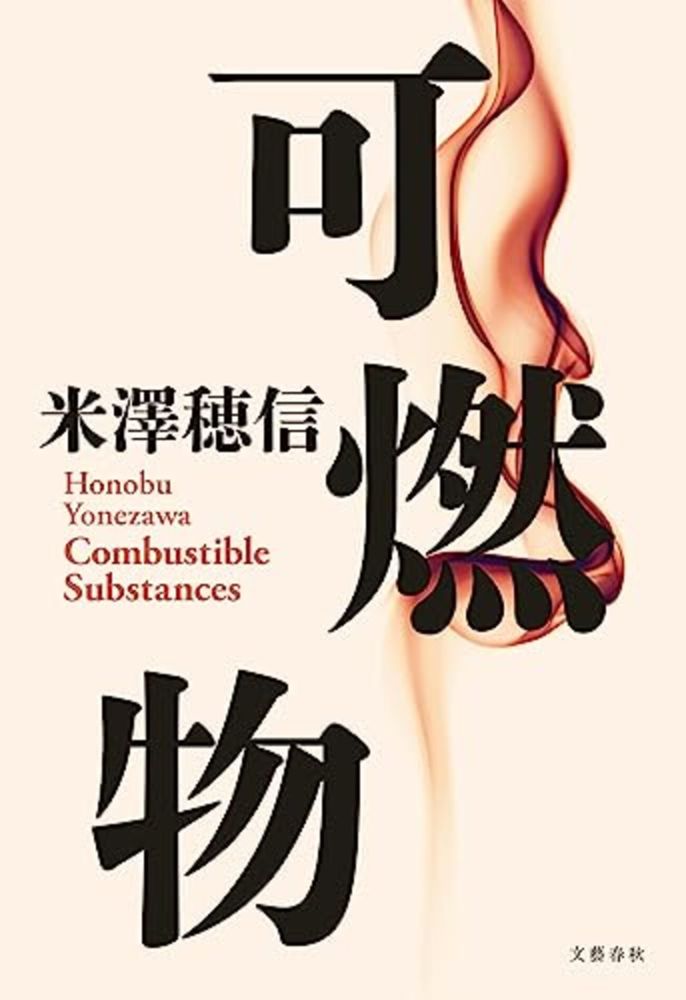あぼがど
@abogard.bsky.social
48 followers
37 following
630 posts
サメよえるオランダ人
Posts
Media
Videos
Starter Packs
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 2d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 3d
うちが最初に認識した首相は大平さんで、大統領はカーター。書記長はブレジネフです。アーウー
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 4d
Reposted by あぼがど
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 5d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 6d
Reposted by あぼがど
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 10d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 10d
あぼがど
@abogard.bsky.social
· 11d