生物画像解析の世界的なネットワークGloBIASを現在準備中なのですが、今後の展開に関心のある方はhttps://t.co/koy4f5oEyMの中の、"GloBIAS"と書かれた場所から、メーリングリストに登録できるので、よろしくお願いします。

Gather | Virtual HQ for Remote Teams
Work remotely side-by-side in digital Spaces that make virtual interactions more human.
gather.town
January 28, 2025 at 3:40 PM
生物画像解析の世界的なネットワークGloBIASを現在準備中なのですが、今後の展開に関心のある方はhttps://t.co/koy4f5oEyMの中の、"GloBIAS"と書かれた場所から、メーリングリストに登録できるので、よろしくお願いします。
生物画像解析の専門家を巡る現状と問題点のまとめ論文。2024年2月にサセックスであった会議で話し合われた内容です。
生物画像解析の専門家の存在意義をあれこれ。
journals.biologists.com/jcs/article/...
生物画像解析の専門家の存在意義をあれこれ。
journals.biologists.com/jcs/article/...

The crucial role of bioimage analysts in scientific research and publication
Summary: We examine the importance of bioimage analysis, obstacles to wider adoption of these important methods and ways to ensure that bioimage analysts receive the career support they need.
journals.biologists.com
January 28, 2025 at 6:33 PM
生物画像解析の専門家を巡る現状と問題点のまとめ論文。2024年2月にサセックスであった会議で話し合われた内容です。
生物画像解析の専門家の存在意義をあれこれ。
journals.biologists.com/jcs/article/...
生物画像解析の専門家の存在意義をあれこれ。
journals.biologists.com/jcs/article/...
4年間に欧州各地で行った生物画像解析学校のレーポートのプルーフ。「作業工程の脱構築」とか書いてしまった。私の世代前後の人だったら理系でもデリダとか知ってるよね…
January 28, 2025 at 4:26 PM
4年間に欧州各地で行った生物画像解析学校のレーポートのプルーフ。「作業工程の脱構築」とか書いてしまった。私の世代前後の人だったら理系でもデリダとか知ってるよね…
これもNEUBIASアカデミーのプログラムです。機械・深層学習で生物画像解析にアプローチする方法。2つのパッケージのそれぞれの開発者が登場します。画素の分類を超える部分の紹介は、複雑な構造を持つ生物システムでは特に鍵となる手法です。要登録・無料。 https://x.com/NEUBIAS_/status/1250948402944389120
January 28, 2025 at 4:20 PM
これもNEUBIASアカデミーのプログラムです。機械・深層学習で生物画像解析にアプローチする方法。2つのパッケージのそれぞれの開発者が登場します。画素の分類を超える部分の紹介は、複雑な構造を持つ生物システムでは特に鍵となる手法です。要登録・無料。 https://x.com/NEUBIAS_/status/1250948402944389120
【再生医療】に関する実験手法を学べる書籍をご紹介します!
・オルガノイドを研究に取り入れたい
・画像データの解析スキルを高めたい
・複数のオミクス解析結果の活かし方を知りたい
といった方にオススメです
目次や詳細はリンクへ↓
決定版 オルガノイド実験スタンダード第2版
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
・オルガノイドを研究に取り入れたい
・画像データの解析スキルを高めたい
・複数のオミクス解析結果の活かし方を知りたい
といった方にオススメです
目次や詳細はリンクへ↓
決定版 オルガノイド実験スタンダード第2版
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...

March 21, 2025 at 12:42 AM
【再生医療】に関する実験手法を学べる書籍をご紹介します!
・オルガノイドを研究に取り入れたい
・画像データの解析スキルを高めたい
・複数のオミクス解析結果の活かし方を知りたい
といった方にオススメです
目次や詳細はリンクへ↓
決定版 オルガノイド実験スタンダード第2版
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
・オルガノイドを研究に取り入れたい
・画像データの解析スキルを高めたい
・複数のオミクス解析結果の活かし方を知りたい
といった方にオススメです
目次や詳細はリンクへ↓
決定版 オルガノイド実験スタンダード第2版
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
さらに続きです。自分たちがどうやって生物画像解析を始めたか、というような話です。これも10分強。お時間のあるかたはどうぞ。
https://www.youtube.com/watch?v=NkT_68azZVw
https://www.youtube.com/watch?v=NkT_68azZVw

第2回 引き続き自己紹介:画像解析とどのように出会ったか
www.youtube.com
January 28, 2025 at 4:26 PM
さらに続きです。自分たちがどうやって生物画像解析を始めたか、というような話です。これも10分強。お時間のあるかたはどうぞ。
https://www.youtube.com/watch?v=NkT_68azZVw
https://www.youtube.com/watch?v=NkT_68azZVw
書籍『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』の詳細はこちらよりご覧いただけます
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...

実験医学別冊:型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
画像解析スキルをさらに高めたい方に! あなたの研究目的にあった画像解析法をデザインするための基本戦略とツールの種類・使い方を「型」で体得する超・実践型教本.コーディング未経験でも,最先端の機械学習・深層学習ツールを取り入れた解析自動化や,バイアスの少ない解析を実現できる力が身に付く.
www.yodosha.co.jp
April 25, 2025 at 4:13 AM
書籍『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』の詳細はこちらよりご覧いただけます
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
実験医学の連載「型で学ぶ生物画像解析」の第二回が公開になりました。今回は550円みたいです。印刷された雑誌の方は店頭にもうならんでいるのかな。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/articles/index.html?ci=64100
これに合わせて、補助資料「Jythonの基礎」をウェブ上で公開しました。https://github.com/miura/jikken_igaku2023/blob/main/20230912JythonBasicsJP.md
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/articles/index.html?ci=64100
これに合わせて、補助資料「Jythonの基礎」をウェブ上で公開しました。https://github.com/miura/jikken_igaku2023/blob/main/20230912JythonBasicsJP.md

型の実践❶:核膜に移行するタンパク質の動態を測定する①
前回までのおさらい前回の序論では次の2点を中心に解説を行った.1つ目は,生物画像解析の実践には作業工程(Workflow)という捉え方とその組み立て方を学ぶことが大切であるという点であった.2点目は,最新のアルゴリズムを使ったプラグインやツールはとても重要だが,それは作業工程の一部を担う部品(Component)であることがほとんどであること,そして,その部品をどのようにして生の画像データから測定までの作業工程に組み込むのか,ということを知らなければ,宝の持ち腐れになる,という点である.こうした点に基づき,この連載では具体的な生物学的課題を取り上げ,作業工程の組み立て方をいわば「型」として紹介し,それが各々の解析の糧となることを期待している.「型」にも理屈があり,それを理解し考え方に慣れることが,自分なりの組み立て方を編み出せるようになるコツである.今回からは核膜に移行するタンパク質の動態の解析を題材に,3回にわたって実際の作業工程の解説を行う.(企画・執筆/三浦耕太,塚田祐基)
www.yodosha.co.jp
January 28, 2025 at 4:36 PM
実験医学の連載「型で学ぶ生物画像解析」の第二回が公開になりました。今回は550円みたいです。印刷された雑誌の方は店頭にもうならんでいるのかな。
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/articles/index.html?ci=64100
これに合わせて、補助資料「Jythonの基礎」をウェブ上で公開しました。https://github.com/miura/jikken_igaku2023/blob/main/20230912JythonBasicsJP.md
https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/articles/index.html?ci=64100
これに合わせて、補助資料「Jythonの基礎」をウェブ上で公開しました。https://github.com/miura/jikken_igaku2023/blob/main/20230912JythonBasicsJP.md
急速に普及しつつあるnapariの紹介文を英国クリック研究所の生物画像解析者、ロッコが書いてくれたので、リンクします。 https://x.com/RogerDAntuono/status/1507019058125762572
January 28, 2025 at 4:31 PM
急速に普及しつつあるnapariの紹介文を英国クリック研究所の生物画像解析者、ロッコが書いてくれたので、リンクします。 https://x.com/RogerDAntuono/status/1507019058125762572
韓国の生物画像解析状況などを仏からソウルに派遣されている人とはなしたんだけど、なんか日本に似ている部分もあっておもしろい。共同でなんかできたらいいんだけどね。
January 28, 2025 at 4:28 PM
韓国の生物画像解析状況などを仏からソウルに派遣されている人とはなしたんだけど、なんか日本に似ている部分もあっておもしろい。共同でなんかできたらいいんだけどね。
昨年夏から、あちこちで教えまくっている。生物画像解析を教えてほしいという需要が基礎医学方面に急激に拡大したためであるが、大学で本腰入れてちゃんとやんなくていいのか、とこちらはさんざんいっているがなかなかそうならんので、困ったものである。http://wiki.cmci.info/mainpages/courses2018
January 28, 2025 at 4:18 PM
昨年夏から、あちこちで教えまくっている。生物画像解析を教えてほしいという需要が基礎医学方面に急激に拡大したためであるが、大学で本腰入れてちゃんとやんなくていいのか、とこちらはさんざんいっているがなかなかそうならんので、困ったものである。http://wiki.cmci.info/mainpages/courses2018
生物画像解析の新しい教科書がオンラインになりました。
"Bioimage Data Analysis Workflow".
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22386-1
EUのサポートにより、オープンクセスです。
"Bioimage Data Analysis Workflow".
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22386-1
EUのサポートにより、オープンクセスです。

Bioimage Data Analysis Workflows
link.springer.com
January 28, 2025 at 4:19 PM
生物画像解析の新しい教科書がオンラインになりました。
"Bioimage Data Analysis Workflow".
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22386-1
EUのサポートにより、オープンクセスです。
"Bioimage Data Analysis Workflow".
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22386-1
EUのサポートにより、オープンクセスです。
ボーデン湖畔の街コンスタンツの大学で10人に一日半、生物画像解析を教える。修士の学生からポスドクまで、ポジションはバラバラ。自分のプロジェクトで喫緊の課題があるひとばかりで食いつきがすごい。

January 28, 2025 at 4:13 PM
ボーデン湖畔の街コンスタンツの大学で10人に一日半、生物画像解析を教える。修士の学生からポスドクまで、ポジションはバラバラ。自分のプロジェクトで喫緊の課題があるひとばかりで食いつきがすごい。
🟡骨格筋の老化によるサルコペニア その理解と戦略
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🟡健康寿命の鍵を握る骨格筋
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🟡健康寿命の鍵を握る骨格筋
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...

実験医学増刊:骨格筋の老化によるサルコペニア その理解と戦略〜筋生物学を超えた総合知で、運動・栄養・創薬による介入をめざす!
加齢に伴う筋肉量・筋力の低下「サルコペニア」.超高齢社会の現代において,その予防や克服が強く求められています.本書はその介入方法の糸口を探るべく,サルコペニアを疫学的に定義し,骨格筋が萎縮する分子メカニズム,また効果的な運動法や他疾患とのかかわりといった,基礎研究から臨床研究までの幅広い視点での最新研究動向をお届けします.骨格筋老化研究の羅針盤となる1冊です.
www.yodosha.co.jp
March 17, 2025 at 4:06 AM
🟡骨格筋の老化によるサルコペニア その理解と戦略
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🟡健康寿命の鍵を握る骨格筋
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🟡健康寿命の鍵を握る骨格筋
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵実験デザインからわかる マルチオミクス研究実践テキスト
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
🔵型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
同じ7/29~8/2、阪大で細胞生物学ワークショップが実施される。
内容は
蛍光顕微鏡の基礎、PSFの測定、蛍光色素、細胞への蛍光色素の導入方法、生きた細胞の観察方法、wide-field蛍光顕微鏡を用いたtime-lapse観察、共焦点顕微鏡を用いたtime-lapse観察、FRAPとFLIP法、photoactivationによる細胞内分子移動度の測定、ImageJを用いた画像解析
らしい。
www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/eventinfo...
内容は
蛍光顕微鏡の基礎、PSFの測定、蛍光色素、細胞への蛍光色素の導入方法、生きた細胞の観察方法、wide-field蛍光顕微鏡を用いたtime-lapse観察、共焦点顕微鏡を用いたtime-lapse観察、FRAPとFLIP法、photoactivationによる細胞内分子移動度の測定、ImageJを用いた画像解析
らしい。
www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/eventinfo...

第35回細胞生物学ワークショップ | 大阪大学大学院生命機能研究科 -FBS-|新しい生物学・生命科学を拓く大学院|おもろい研究!君ならできる、ここでできる
大阪大学大学院生命機能研究科 -FBS-の「セミナー・イベント詳細」のページです。講演者、日時、場所、対象者、演題などの詳しい情報をご紹介します。
www.fbs.osaka-u.ac.jp
May 5, 2024 at 4:04 PM
同じ7/29~8/2、阪大で細胞生物学ワークショップが実施される。
内容は
蛍光顕微鏡の基礎、PSFの測定、蛍光色素、細胞への蛍光色素の導入方法、生きた細胞の観察方法、wide-field蛍光顕微鏡を用いたtime-lapse観察、共焦点顕微鏡を用いたtime-lapse観察、FRAPとFLIP法、photoactivationによる細胞内分子移動度の測定、ImageJを用いた画像解析
らしい。
www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/eventinfo...
内容は
蛍光顕微鏡の基礎、PSFの測定、蛍光色素、細胞への蛍光色素の導入方法、生きた細胞の観察方法、wide-field蛍光顕微鏡を用いたtime-lapse観察、共焦点顕微鏡を用いたtime-lapse観察、FRAPとFLIP法、photoactivationによる細胞内分子移動度の測定、ImageJを用いた画像解析
らしい。
www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/eventinfo...
特にcall4helpは参加者が直前まで、生物画像解析の質問の登録ができます。call4helpについては上のブログに特に詳しくどのような感じなのかを説明しました。call4helpの専用サイトは以下です。
call4help.let-your-data-speak.com
call4help.let-your-data-speak.com

Call4help
This is a webpage used to present Image Analysis problems to the broader community.
call4help.let-your-data-speak.com
September 10, 2025 at 5:40 PM
特にcall4helpは参加者が直前まで、生物画像解析の質問の登録ができます。call4helpについては上のブログに特に詳しくどのような感じなのかを説明しました。call4helpの専用サイトは以下です。
call4help.let-your-data-speak.com
call4help.let-your-data-speak.com
先週EMBLでも話したけどプログラミングがうまくなっても生物画像解析がうまくなるわけではないので、このあたりのことはよく周知される必要があると思っています。ランボルギーニ買ったから早く走れるかというとそうでもない。
January 28, 2025 at 4:36 PM
先週EMBLでも話したけどプログラミングがうまくなっても生物画像解析がうまくなるわけではないので、このあたりのことはよく周知される必要があると思っています。ランボルギーニ買ったから早く走れるかというとそうでもない。
先月発行した書籍『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』の執筆者の多くが関わるGloBIASによる国際的な生物画像解析学会(トレーニングスクール,ハッカソン,シンポジウムなど)が,10月に理研神戸キャンパスで開催されます.詳細はリンク先をご覧ください.
www.globias.org/activities/b...
www.globias.org/activities/b...
April 25, 2025 at 4:13 AM
先月発行した書籍『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』の執筆者の多くが関わるGloBIASによる国際的な生物画像解析学会(トレーニングスクール,ハッカソン,シンポジウムなど)が,10月に理研神戸キャンパスで開催されます.詳細はリンク先をご覧ください.
www.globias.org/activities/b...
www.globias.org/activities/b...
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari 実験医学別冊 が、紀伊國屋電子書籍ストアで販売開始されました。
5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...
5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...
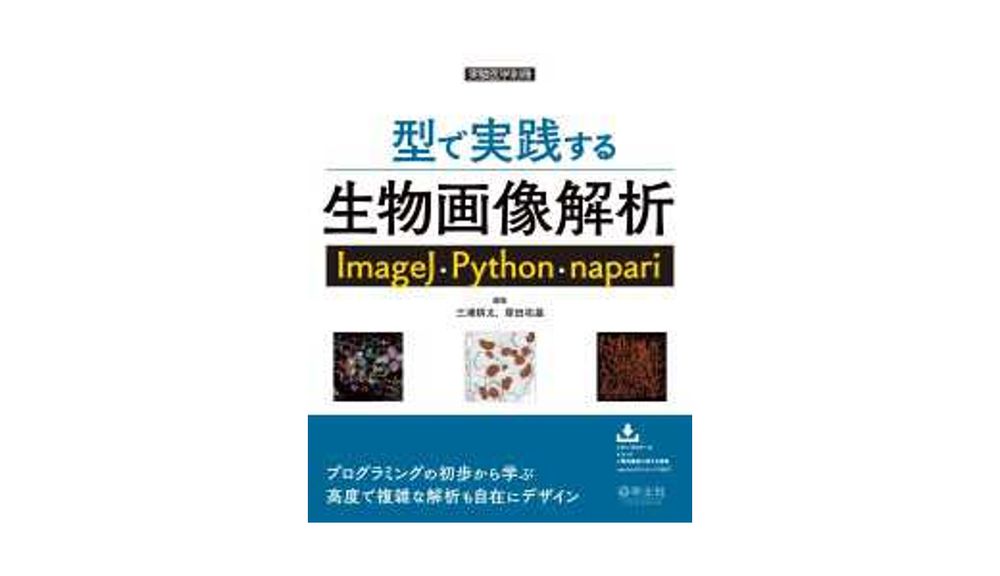
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari 実験医学別冊
著者:三浦耕太(編)/塚田祐基(編) 出版:株式会社羊土社 2025/3/28(金)配信
5leaf.jp
March 28, 2025 at 5:42 AM
型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari 実験医学別冊 が、紀伊國屋電子書籍ストアで販売開始されました。
5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...
5leaf.jp/kinokuniya/dsg-08-EK...
サセックスの由緒あるホテルで生物画像解析の会議。30人ほどの参加者で4日間の討議(というか合宿)をしました。半分は若手の院生やポスドクで、全員と知り合いになれました。残りの半分はNEUBIASの常連。 https://x.com/Co_Biologists/status/1758418811483509121
January 28, 2025 at 3:40 PM
サセックスの由緒あるホテルで生物画像解析の会議。30人ほどの参加者で4日間の討議(というか合宿)をしました。半分は若手の院生やポスドクで、全員と知り合いになれました。残りの半分はNEUBIASの常連。 https://x.com/Co_Biologists/status/1758418811483509121
なかなかの盛況でした。生物画像解析に興味がある、あるいはある程度の専門性がある、という方で、目下準備中のGloBIAS(生物画像解析の世界的なネットワーク)に関心がある方は、以下のフォームにメールアドレスを登録してもらえたら、準備状況などを以後連絡します。https://forms.gle/8czuYrqChBVYJxLU9

GloBIAS interest
Dear Participant,
Thank you for participating in the image.sc LIVE! Around the World event.
If you would like to get information about now building GloBIAS, the worldwide network of those who are interested in Bioimage Analysis, please tell me your email and the location where you are working!
Thank you for your time and consideration.
Sincerely,
GloBIAS team
forms.gle
January 28, 2025 at 3:40 PM
なかなかの盛況でした。生物画像解析に興味がある、あるいはある程度の専門性がある、という方で、目下準備中のGloBIAS(生物画像解析の世界的なネットワーク)に関心がある方は、以下のフォームにメールアドレスを登録してもらえたら、準備状況などを以後連絡します。https://forms.gle/8czuYrqChBVYJxLU9
『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』詳細はこちら↓
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...

実験医学別冊:型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari
画像解析スキルをさらに高めたい方に! あなたの研究目的にあった画像解析法をデザインするための基本戦略とツールの種類・使い方を「型」で体得する超・実践型教本.コーディング未経験でも,最先端の機械学習・深層学習ツールを取り入れた解析自動化や,バイアスの少ない解析を実現できる力が身に付く.
www.yodosha.co.jp
October 14, 2025 at 7:28 AM
『型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari』詳細はこちら↓
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/...
学研から出した「ImageJで学ぶ生物画像解析」は2016年に出版し、けっこうな評判になりました。その後、続編的な本を出版しようと考えていたのですがついにその願いをはたすことができた、という感じです。
March 18, 2025 at 4:39 AM
学研から出した「ImageJで学ぶ生物画像解析」は2016年に出版し、けっこうな評判になりました。その後、続編的な本を出版しようと考えていたのですがついにその願いをはたすことができた、という感じです。
実験医学(羊土社)10月号から、生物画像解析のImageJ上級者向けの連載を塚田さんと始めます。題して「実践ImageJ 型で学ぶ生物画像解析」よろしく!
https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758125727/
https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758125727/

実験医学:AlphaFoldの可能性と挑戦〜すぐ始められる構造・機能予測から、複合体予測やタンパク質デザインへの応用まで
構造生物学に革命をもたらしたAI「AlphaFold」は何ができて何ができないのか?Webですぐに活用する方法や,AI時代の研究戦略を解説/膨大な研究データを保管するためのラボ内サーバー構築ノウハウ
www.yodosha.co.jp
January 28, 2025 at 4:35 PM
実験医学(羊土社)10月号から、生物画像解析のImageJ上級者向けの連載を塚田さんと始めます。題して「実践ImageJ 型で学ぶ生物画像解析」よろしく!
https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758125727/
https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758125727/
内容的には生物画像解析をなるべくPythonの文法のスクリプトとして記述する、ということを主眼においています。これは、手法の再現性のために手法を正確に記述する、ということがその第一の目的です。
March 18, 2025 at 4:39 AM
内容的には生物画像解析をなるべくPythonの文法のスクリプトとして記述する、ということを主眼においています。これは、手法の再現性のために手法を正確に記述する、ということがその第一の目的です。

