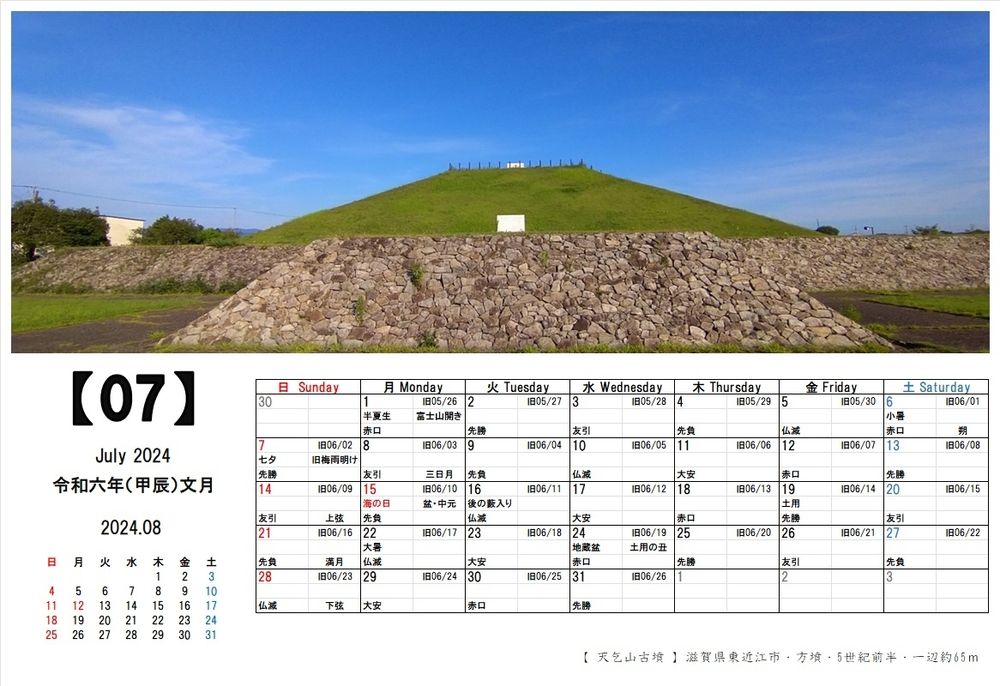#考古学のおやつ 1/1
滋賀県守山市・阿比留遺跡(あびるいせき)で、古墳の周溝から6世紀初めごろの石見型木製品。コウヤマキ製。守山市教育委員会の調査。
[朝日新聞]
www.asahi.com/articles/AST...

#考古学のおやつ 1/1
滋賀県守山市・阿比留遺跡(あびるいせき)で、古墳の周溝から6世紀初めごろの石見型木製品。コウヤマキ製。守山市教育委員会の調査。
[朝日新聞]
www.asahi.com/articles/AST...
石見型木製品は、奈良県の石見遺跡で見つかった特異な形状の埴輪に由来する。これは以前、盾と⇨考えられていたが、近年は儀仗という説が有力になっているようだ。
今井邦彦氏が指摘されているが、わかりやすいように「木の埴輪」と呼んでいるだけで、考古学では主に「木製立物」と呼ぶ。ただ、世間では浸透しておらず、喩えである「木の埴輪」が独り歩きしている。
www.asahi.com/articles/AST...

石見型木製品は、奈良県の石見遺跡で見つかった特異な形状の埴輪に由来する。これは以前、盾と⇨考えられていたが、近年は儀仗という説が有力になっているようだ。
今井邦彦氏が指摘されているが、わかりやすいように「木の埴輪」と呼んでいるだけで、考古学では主に「木製立物」と呼ぶ。ただ、世間では浸透しておらず、喩えである「木の埴輪」が独り歩きしている。
www.asahi.com/articles/AST...
記事で触れられている「前方後方墳近江起源説」は植田文雄先生あたりが出どころではなかったかと思うが、近江から東方への伝播ルートは想定できるものの、起源かどうかはまだ一考の余地がありそうにも思う。神郷亀塚古墳(東近江市)や冨波古墳(野洲市)の存在は無視できないが、ややこしいことに纒向遺跡にも1基あるのである(メクリ1号墳)。
しかし前方後方墳は扱いが悩ましい。
www.sankei.com/article/2025...

記事で触れられている「前方後方墳近江起源説」は植田文雄先生あたりが出どころではなかったかと思うが、近江から東方への伝播ルートは想定できるものの、起源かどうかはまだ一考の余地がありそうにも思う。神郷亀塚古墳(東近江市)や冨波古墳(野洲市)の存在は無視できないが、ややこしいことに纒向遺跡にも1基あるのである(メクリ1号墳)。
しかし前方後方墳は扱いが悩ましい。
www.sankei.com/article/2025...
#考古学のおやつ 1/1
滋賀県守山市・笠原南遺跡(かさはらみなみいせき)で、弥生時代末~古墳時代初頭の溝・井戸・掘立柱建物・周溝墓など。滋賀県文化財保護協会の調査。10/5現地説明会。
[滋賀県文化財保護協会]
www.shiga-bunkazai.jp/news/%e5%ae%...

#考古学のおやつ 1/1
滋賀県守山市・笠原南遺跡(かさはらみなみいせき)で、弥生時代末~古墳時代初頭の溝・井戸・掘立柱建物・周溝墓など。滋賀県文化財保護協会の調査。10/5現地説明会。
[滋賀県文化財保護協会]
www.shiga-bunkazai.jp/news/%e5%ae%...
#考古学のおやつ 1/1
滋賀県長浜市・葛籠尾崎湖底遺跡(つづらおざきこていいせき)で、琵琶湖の水深65m地点から古墳時代の土師器6個。同一地点に同時代の同形同大の土器が多数集積することから、船の積荷がそのまま水没した可能性が高い。
[立命館大学]
www.ritsumei.ac.jp/profile/pres...
#考古学のおやつ 1/1
滋賀県長浜市・葛籠尾崎湖底遺跡(つづらおざきこていいせき)で、琵琶湖の水深65m地点から古墳時代の土師器6個。同一地点に同時代の同形同大の土器が多数集積することから、船の積荷がそのまま水没した可能性が高い。
[立命館大学]
www.ritsumei.ac.jp/profile/pres...

www3.nhk.or.jp/news/html/20...

www3.nhk.or.jp/news/html/20...
www3.nhk.or.jp/news/html/20...

www3.nhk.or.jp/news/html/20...
#考古学のおやつ 1/1
滋賀県長浜市・葛籠尾崎湖底遺跡(つづらおざきこていいせき)で、琵琶湖の水深70mの湖底から古墳時代の高坏。
[朝日新聞]
www.asahi.com/articles/AST...

#考古学のおやつ 1/1
滋賀県長浜市・葛籠尾崎湖底遺跡(つづらおざきこていいせき)で、琵琶湖の水深70mの湖底から古墳時代の高坏。
[朝日新聞]
www.asahi.com/articles/AST...
滋賀県高島市の上御殿遺跡で、弥生時代後期から古墳時代前期にかけて約200年間続いた地域の拠点集落の跡を確認したとのこと。
この遺跡では古代の中国北部に分布した「オルドス式銅剣」の特徴を持つ短剣の鋳型が国内で初めて出土しており、その由来や年代を知る手掛かりが得られることが期待されたが、残念ながらそれは果たせなかったらしい。
とはいえ、日本海側の地域の特徴を持つ土器など、遠隔地との交流があったことを示す資料が見つかったことは重要で、そうした交易の過程で上記の鋳型も流入した可能性はあると見ていいと思う。
news.yahoo.co.jp/articles/2f3...

滋賀県高島市の上御殿遺跡で、弥生時代後期から古墳時代前期にかけて約200年間続いた地域の拠点集落の跡を確認したとのこと。
この遺跡では古代の中国北部に分布した「オルドス式銅剣」の特徴を持つ短剣の鋳型が国内で初めて出土しており、その由来や年代を知る手掛かりが得られることが期待されたが、残念ながらそれは果たせなかったらしい。
とはいえ、日本海側の地域の特徴を持つ土器など、遠隔地との交流があったことを示す資料が見つかったことは重要で、そうした交易の過程で上記の鋳型も流入した可能性はあると見ていいと思う。
news.yahoo.co.jp/articles/2f3...
滋賀県高島市安曇川町田中の上御殿(かみごてん)遺跡で弥生時代後期から古墳時代前期にかけて(2~3世紀)の竪穴建物跡群が見つかり、県文化財保護協会が17日発表した。湖南地域の土器や湖東地域の石材で作られた砥石、日本海側の丹後・若狭地域の土器も出土し、女王・卑弥呼が活躍した2世紀末~3世紀中頃の邪馬台国時代に、同遺跡が琵琶湖や日本海を通じた交流拠点だったことをうかがわせる成果だという。
#上御殿遺跡 #邪馬台国

#考古学のおやつ 1/1
滋賀県高島市・上御殿遺跡(かみごてんいせき)で、弥生時代後期~古墳時代前期の200年間続いた地域の拠点集落跡を確認。滋賀県文化財保護協会7/17発表。
[共同通信]
www.47news.jp/12875992.html

#考古学のおやつ 1/1
滋賀県高島市・上御殿遺跡(かみごてんいせき)で、弥生時代後期~古墳時代前期の200年間続いた地域の拠点集落跡を確認。滋賀県文化財保護協会7/17発表。
[共同通信]
www.47news.jp/12875992.html
滋賀県甲賀市水口にある郷土資料館。水口祭の曳山、古墳時代の出土品、水口藩や水口宿の関係資料、民具などを展示。巖谷一六・小波記念室を併設する。
#甲賀水口
#地域文化
#資料館
https://www.livewalker.com/web/detail/30911

滋賀県甲賀市水口にある郷土資料館。水口祭の曳山、古墳時代の出土品、水口藩や水口宿の関係資料、民具などを展示。巖谷一六・小波記念室を併設する。
#甲賀水口
#地域文化
#資料館
https://www.livewalker.com/web/detail/30911
退職後の男性が大半で、仲間内で固まるような独特の雰囲気だったので(草刈り機のうんちくを作業中に横で語りたがる困った人がいたり)、次はもう行かないだろうな…ボランティア参加なので。こんな風に色々試行錯誤しながらやっています。
この4月に撮影して、残しておきたかった古墳話をブログで更新しました。
↓
専門家と一緒に堅田丘陵の春日山古墳群(国史跡)を歩く #katata堅田 #滋賀県 #大津市
入院中の家族の病状はいくぶん持ち直しましたが、今の治療の第1クールが終わった後は入退院と通院(あるいは転院)を繰り返すことになりそうです。
下記は4月撮影分で、今のうちに掲載しておこうと思い更新します。(次回は堅田丘陵の春日山古墳群(国史跡)掲載を予定しています。)今後の撮影予定等ありますので、撮影は普段通り続けていきます。
堅田内湖の傍の路地に見事な地蔵堂、空を見上げれば堅田の落雁 #katata堅田 #滋賀県 #大津市
古墳巡りの参考にしているサイトのひとつ『古墳とかアレ』の管理人氏も同じ経験があるらしい。
古墳は石材の転用を目的として破壊されることがあり、石室が半壊している場合(天井石がないなど)は近隣の城などに転用されているのではないかと思っているが、よくわからないのが「奥壁がなくなっている」事例で、墳丘が残っている場合はどうやって抜き取ったのかが不思議である(天井石もあるし)。
古墳巡りの参考にしているサイトのひとつ『古墳とかアレ』の管理人氏も同じ経験があるらしい。
古墳は石材の転用を目的として破壊されることがあり、石室が半壊している場合(天井石がないなど)は近隣の城などに転用されているのではないかと思っているが、よくわからないのが「奥壁がなくなっている」事例で、墳丘が残っている場合はどうやって抜き取ったのかが不思議である(天井石もあるし)。
滋賀県立安土城考古博物館であった、人と馬の関係をテーマにした展覧会(名称忘れた)より。
左は栗東市新開1号墳出土の馬具、右は野洲市御明田古墳群出土の馬形埴輪と人物埴輪(馬丁)。


滋賀県立安土城考古博物館であった、人と馬の関係をテーマにした展覧会(名称忘れた)より。
左は栗東市新開1号墳出土の馬具、右は野洲市御明田古墳群出土の馬形埴輪と人物埴輪(馬丁)。

一瞬だけど滋賀県In。
無人駅だけどICOCAに対応してくれてて助かった。
街道筋だなぁと思う古いお家がたくさんあって、時代劇好きには目の保養❤️
(新しい老人ホームも結構多いのがびっくり)
帰りは浜大津からの京阪電車。
こっちは障害者手帳の福祉乗車証が使えないのでICOCAで。
京都市側は、音羽と四ノ宮が入り混じる変な地域。
諸刃神社の社務所を途中に発見。
社務所地域は、古墳群だった。
髭茶屋町の通りは、旧東海道筋。
バスの無い日の行き方の確認が出来た。



一瞬だけど滋賀県In。
無人駅だけどICOCAに対応してくれてて助かった。
街道筋だなぁと思う古いお家がたくさんあって、時代劇好きには目の保養❤️
(新しい老人ホームも結構多いのがびっくり)
帰りは浜大津からの京阪電車。
こっちは障害者手帳の福祉乗車証が使えないのでICOCAで。
京都市側は、音羽と四ノ宮が入り混じる変な地域。
諸刃神社の社務所を途中に発見。
社務所地域は、古墳群だった。
髭茶屋町の通りは、旧東海道筋。
バスの無い日の行き方の確認が出来た。