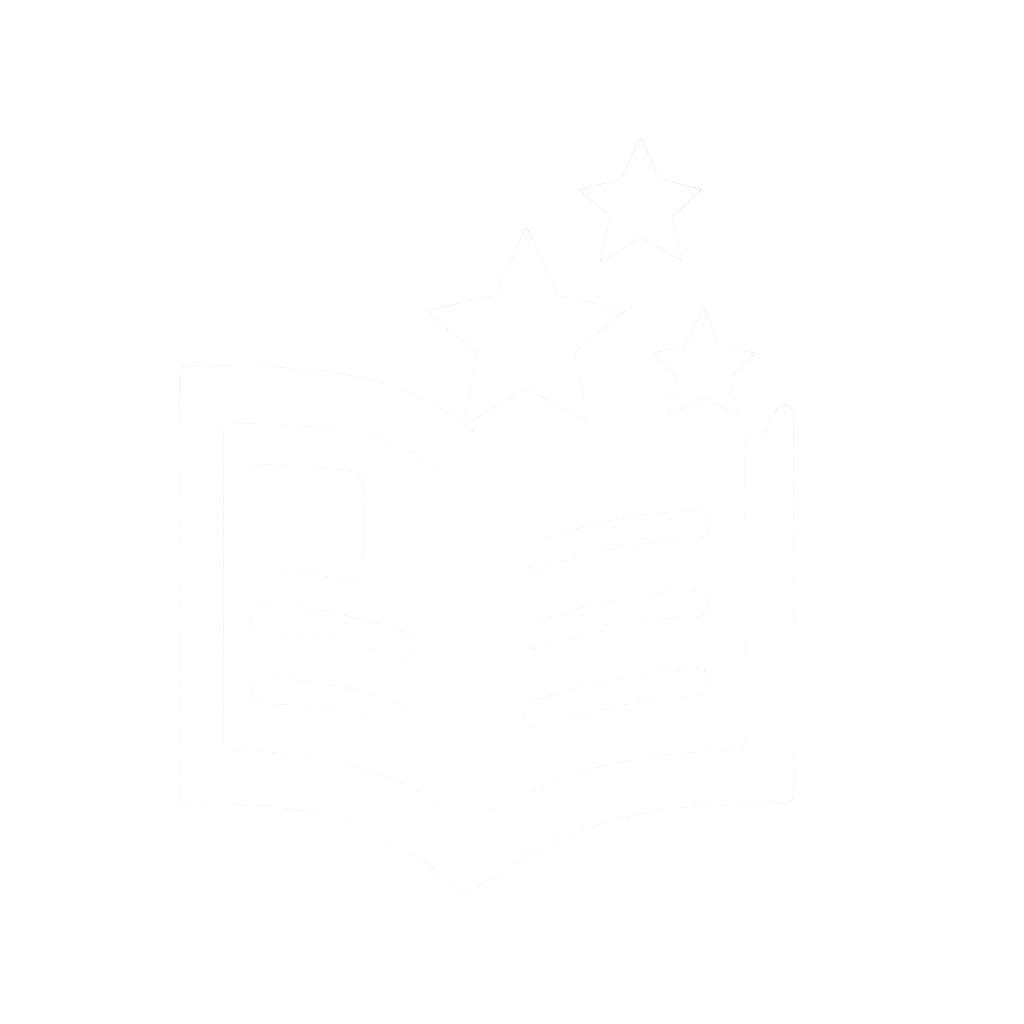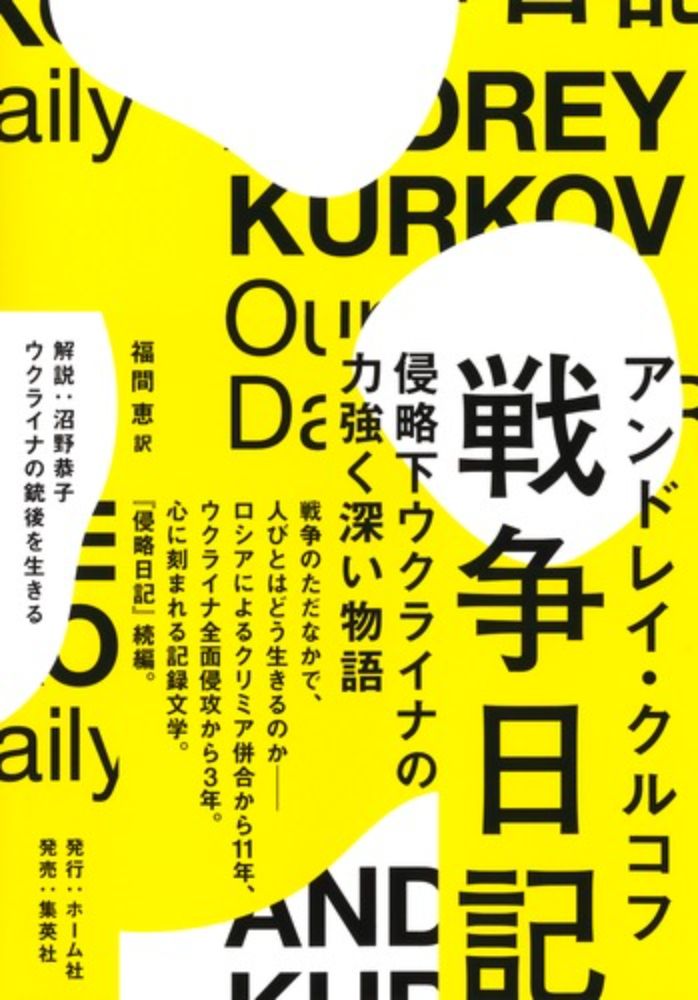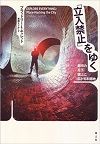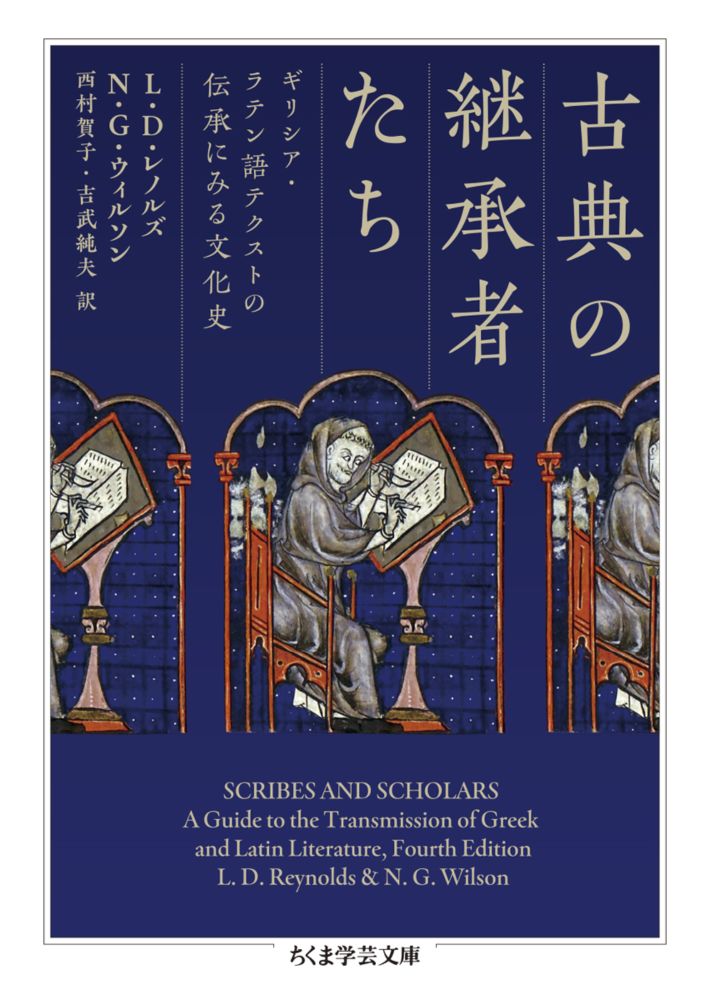Posts
Media
Videos
Starter Packs
Reposted by tatumi
tatumi
@norinagatatumi.bsky.social
· Aug 15

悩んでもがいて、作家になった彼女たち-淡交社 本のオンラインショップ
日本の近代から現代文学を彩った、タフな女の作家たちを検証!
「スキャンダル」「低収入独身」「親ガチャ」……現代人たちが抱えている問題について、近現代の女性作家たちも同じように 悩んでいた!
平安時代の女性作家を新たな視点で紹介し、多くの共感を得た『平安女子は、みんな必死で恋してた』(2020)。今度は近現代の女性の作家に迫る一冊。前著に劣らぬ新解釈とともに、「低収入」「親ガチャ」など、現代のさま...
www.book.tankosha.co.jp