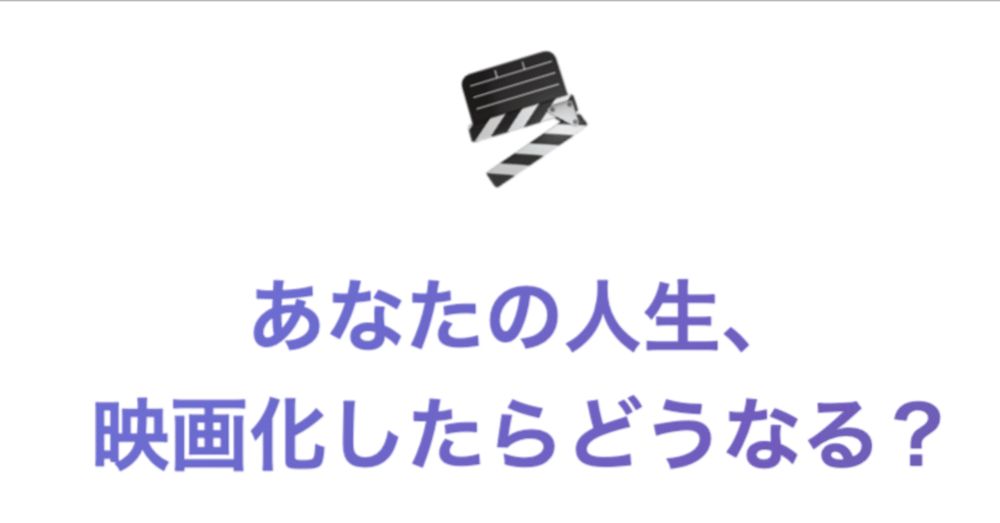バイナリエディタなんとか作れた。超シンプルかつvanillaで作らないときつそうだなこれ系。
バイナリエディタなんとか作れた。超シンプルかつvanillaで作らないときつそうだなこれ系。

というか作りが雑なんだよな、Googleのサービスは何もかも。。。
というか作りが雑なんだよな、Googleのサービスは何もかも。。。
「絶対儲かる」とかいう下心というか皮算用があるためついついログイン機能を最初から入れてしまうが、99%無駄になるので入れるべきではない。ログイン機能入れるとしてもヒットしてからでいい。
「絶対儲かる」とかいう下心というか皮算用があるためついついログイン機能を最初から入れてしまうが、99%無駄になるので入れるべきではない。ログイン機能入れるとしてもヒットしてからでいい。