つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
34 followers
23 following
210 posts
https://morinaoto.hatenadiary.jp/
社会学 教育 歴史 階層階級 筋トレ 千葉ロッテマリーンズ 和田康士朗 TVXQ NCT
Posts
Media
Videos
Starter Packs
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· 24d

社会政策学会・労働史部会研究会報告(2025年9月13日 於:法政大学市ヶ谷キャンパス) - shinichiroinaba's blog
社会政策学会・労働史部会研究会(2025年9月13日) 稲葉振一郎『市民社会論の再生 ポスト戦後日本の労働・教育研究』について 報告資料 稲葉振一郎(明治学院大学) 「つけ加えておきますと、若い人はまた労働問題研究になっています。ただし、かつてのような労働問題研究ではなく、非正規労働であったり、過労死であったり、女性労働問題などです。労働は問題なのです。しかしその問題は、兵藤さんたちが氏原さんから...
shinichiroinaba.hatenablog.com
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 16

『市民社会論の再生』合評会のコメント2本 - もどきの部屋 education, sociology, history
前回のエントリ(稲葉振一郎『市民社会論の再生――ポスト戦後日本の労働・教育研究』合評会に登壇します - もどきの部屋 education, sociology, history)で超絶ショートノティスとなりました社会政策学会・労働史部会での稲葉振一郎著『市民社会論の再生――ポスト戦後日本の労働・教育研究』(春秋社、2024年)の合評会に参加してきました。参加者はそれほど多くありませんでしたが(そう...
morinaoto.hatenadiary.jp
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 13
重いから持っていかない。
明日の社会政策学会・労働史部会の『市民社会論の再生:ポスト戦後日本の労働・教育研究』(稲葉振一郎著、春秋社、2024年)合評会では、労働(史)研究者たちに「必読文献です」と脅しをかけるじゃなくて営業するために紙版著書2冊の現物を持ち込む所存。
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 13
明日の社会政策学会・労働史部会の『市民社会論の再生:ポスト戦後日本の労働・教育研究』(稲葉振一郎著、春秋社、2024年)合評会では、労働(史)研究者たちに「必読文献です」と脅しをかけるじゃなくて営業するために紙版著書2冊の現物を持ち込む所存。


つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 13
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 13
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 12
直前までかかってまるっとコメント2本分のレジュメを作成してしまった。(わたくしはいったいなにをしているのか
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 12
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 11
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 11
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 11
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Sep 3

稲葉振一郎『市民社会論の再生――ポスト戦後日本の労働・教育研究』合評会に登壇します - もどきの部屋 education, sociology, history
どの程度オープンな会なのかそうでないのかが読み切れなかったので控えていましたが、一応 Facebook の「社会政策学会 研究者育成フォーラム」なるグループは「公開」設定で出しているようなので――社会政策学会 研究者育成フォーラム | 労働史部会・世話人の梅崎修です――ここでも告知します(直前でもあるのでもはやそんな気にするほどの影響はないでしょう)。きたる9月13日(土)に社会政策学会労働史部会...
morinaoto.hatenadiary.jp
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Aug 6

岡野・佐久間(2023)「公教育再考」とRED研2巻本とのあいだ - もどきの部屋 education, sociology, history
RED研2巻本が世にでた2024年9月に1年ほどさきだつ2023年8月、世織書房から『教育学年報14 公教育を問い直す』(佐久間亜紀ほか編)が刊行されている。特集テーマはそのものズバリ、「公教育を問い直す」である。巻頭には政治学・ジェンダー研究者の岡野八代さんと第14号のゲストエディターである教育学者の佐久間亜紀さんとの対談が掲載されている。タイトルは「公教育再考――ケアをめぐる政治学と教育学の交...
morinaoto.hatenadiary.jp
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Aug 4
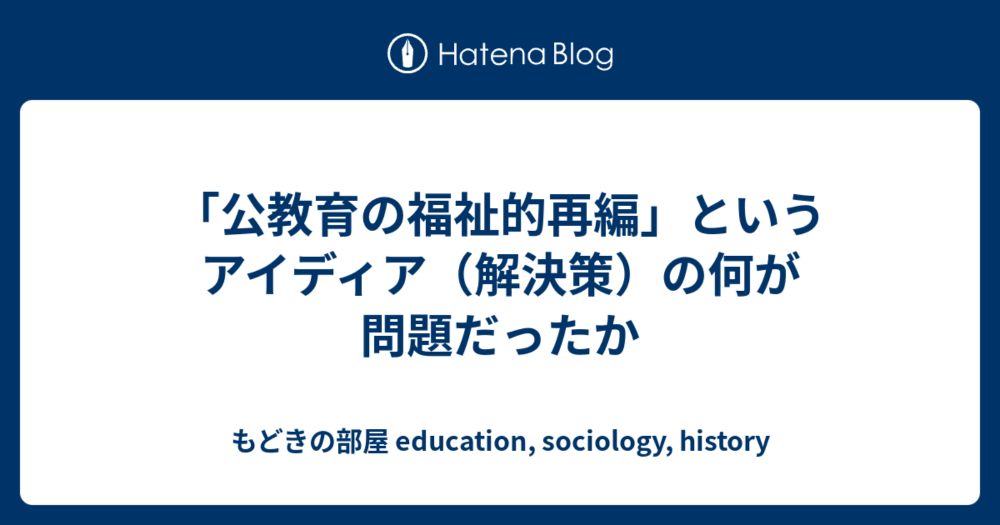
「公教育の福祉的再編」というアイディア(解決策)の何が問題だったか - もどきの部屋 education, sociology, history
RED研の著書企画が浮上するはるか昔、7年前の2018年に、RED研内部の別動隊として「福祉的再編を基軸とした次世代型公教育システムの開発」というタイトルの共同研究が走り始めたことがある。それに対して、RED研のメンバー(=RED研メーリングリスト登録者)のひとりだった――そして上記「別動隊」には入っていなかった――Sさんから、かなり激しい違和感の表明を受けた。当時、私はSさんの問題提起をほんとう...
morinaoto.hatenadiary.jp
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 31
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 31
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 31
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 31
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 27
つくばのくま
@mrnaoto.bsky.social
· Jul 26


