
メインのnoteアカウント:https://note.com/takeuchi_kazuto
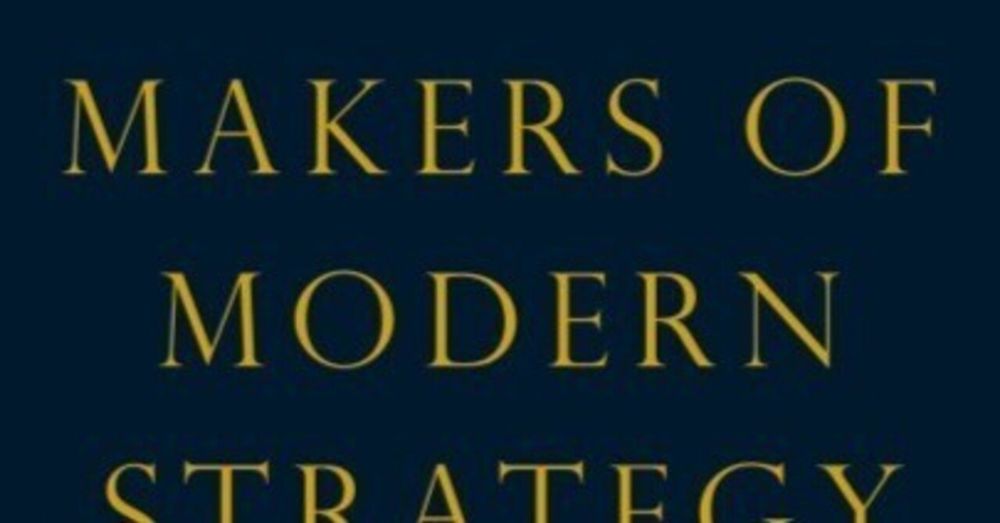
戦略思想の歴史を学ぶThe New Makers of Modern Strategy (2023)の紹介
note.com/takeuchi_kaz...
www.bbc.com/japanese/art...
1/

www.bbc.com/japanese/art...
1/
whitehouse.gov/wp-content/u...
1/
whitehouse.gov/wp-content/u...
1/
米国はロシアと交渉した和平案をウクライナに強制しようとしてきましたが、欧州はウクライナに不利な提案を阻んできました。
www.afpbb.com/articles/-/3...
1/

米国はロシアと交渉した和平案をウクライナに強制しようとしてきましたが、欧州はウクライナに不利な提案を阻んできました。
www.afpbb.com/articles/-/3...
1/
www.jiji.com/jc/article?k...

www.jiji.com/jc/article?k...
youtu.be/nFKqQoS1JDs

youtu.be/nFKqQoS1JDs
www.afpbb.com/articles/-/3...

www.afpbb.com/articles/-/3...
今月だと米国から台湾に中距離防空ミサイルNASAMSを3基売却することで合意しています。1/
www.yomiuri.co.jp/world/202511...

今月だと米国から台湾に中距離防空ミサイルNASAMSを3基売却することで合意しています。1/
www.yomiuri.co.jp/world/202511...
www.bbc.com/japanese/art...

www.bbc.com/japanese/art...
www.nikkei.com/article/DGXZ...

www.nikkei.com/article/DGXZ...
イランの核施設攻撃を思い出させる深刻な状況なので、最近この方面には注目しています。
x.com/flightradar2...

イランの核施設攻撃を思い出させる深刻な状況なので、最近この方面には注目しています。
x.com/flightradar2...


www.nikkei.com/article/DGXZ...

www.nikkei.com/article/DGXZ...
新和平案に米国の軍事支援の縮小、対ロシア制裁の解除などウクライナに厳しい内容が含まれています。
1/
www.bbc.com/japanese/art...

新和平案に米国の軍事支援の縮小、対ロシア制裁の解除などウクライナに厳しい内容が含まれています。
1/
www.bbc.com/japanese/art...
www.afpbb.com/articles/-/3...

www.afpbb.com/articles/-/3...
東アジアの地理環境と精密誘導の軍事技術の影響を踏まえ、一定の敷居を超えない烈度で限定戦争となる可能性があることを論じています。1/
doi.org/10.1162/ISEC...

東アジアの地理環境と精密誘導の軍事技術の影響を踏まえ、一定の敷居を超えない烈度で限定戦争となる可能性があることを論じています。1/
doi.org/10.1162/ISEC...
reut.rs/3JEA4dn
1/

reut.rs/3JEA4dn
1/
中国が自らの立場を主張することは当然のことですが、適切な作法と言葉遣いを用いなければ正常な外交の妨げとなってしまいます。1/
www.nikkei.com/article/DGXZ...

中国が自らの立場を主張することは当然のことですが、適切な作法と言葉遣いを用いなければ正常な外交の妨げとなってしまいます。1/
www.nikkei.com/article/DGXZ...
半導体生産拠点の新林サイエンスパークが攻撃された場合、台湾の推計で世界経済のGDPは6%から10%減、復旧に3年と見積もられています。
日経 台湾半導体、防空を懸念
www.nikkei.com/article/DGKK...
台湾は30年までに国防予算をGDP比で5%に引き上げる予定で、防空システムの近代化に取り組んでいます。
生産基盤だけでなく、貨物の輸送に用いる港湾など交通基盤に対する脅威も想定する必要があるでしょう。

半導体生産拠点の新林サイエンスパークが攻撃された場合、台湾の推計で世界経済のGDPは6%から10%減、復旧に3年と見積もられています。
日経 台湾半導体、防空を懸念
www.nikkei.com/article/DGKK...
台湾は30年までに国防予算をGDP比で5%に引き上げる予定で、防空システムの近代化に取り組んでいます。
生産基盤だけでなく、貨物の輸送に用いる港湾など交通基盤に対する脅威も想定する必要があるでしょう。
まず、国家の安全保障のためには、その脅威の程度に応じた軍事的能力を持つことが基本となります。同盟を用いない中立主義が選択できるのは、自国負担だけで脅威に対応できる見込みがある場合であって、それが実現可能であるかどうかは各国の保有国力、地理環境、軍事技術などで左右されます。
1/
まず、国家の安全保障のためには、その脅威の程度に応じた軍事的能力を持つことが基本となります。同盟を用いない中立主義が選択できるのは、自国負担だけで脅威に対応できる見込みがある場合であって、それが実現可能であるかどうかは各国の保有国力、地理環境、軍事技術などで左右されます。
1/
「中国外務省の林建報道官は、高市首相が7日の国会答弁で台湾有事が日本の集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」になり得ると述べたことについて、「日本の関係者による両岸問題への干渉は中日関係に深刻な打撃を与える」と警告」
youtu.be/NFMNqMvvTos

「中国外務省の林建報道官は、高市首相が7日の国会答弁で台湾有事が日本の集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」になり得ると述べたことについて、「日本の関係者による両岸問題への干渉は中日関係に深刻な打撃を与える」と警告」
youtu.be/NFMNqMvvTos
www.sankei.com/article/2025...

www.sankei.com/article/2025...
direct.mit.edu/isec/article...
1/

direct.mit.edu/isec/article...
1/
www.asahi.com/articles/AST...

www.asahi.com/articles/AST...
www.sankei.com/article/2025...

www.sankei.com/article/2025...

