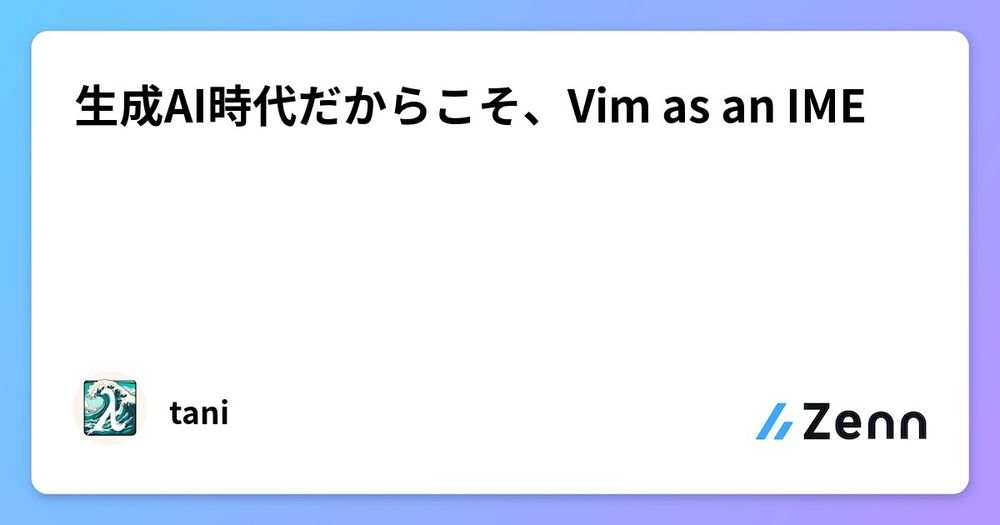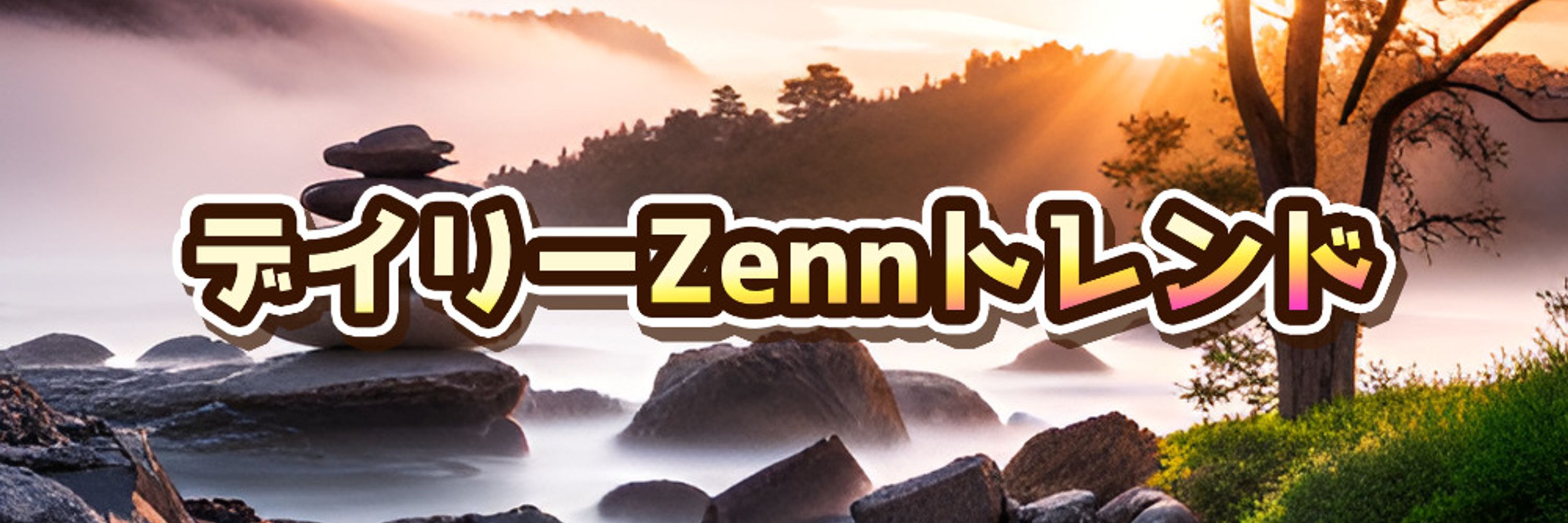
ソースコードの配布は「 https://github.com/aegisfleet/zenn-trending-to-bluesky 」で行っています。
Qiitaトレンド: @dailyqiitatrends.bsky.social
GitHubトレンド: @dailygithubtrends.bsky.social
緯度経度からの住所検索!〜日本の住所に絶望し、希望を見つけるまで〜
LayerXのエンジニアが、緯度経度から住所を特定する機能開発の苦労と解決策を綴る。
当初は外部API利用を検討したが、日本の住所の複雑さとAPIの精度問題に直面。
最終的に国土地理院の「位置参照情報」を活用し、自社DB構築とGeohashによるキャッシュ戦略で精度100%を実現。
コストと精度のバランスを取りながら、ユーザー体験を重視した開発プロセスが語られる。

緯度経度からの住所検索!〜日本の住所に絶望し、希望を見つけるまで〜
LayerXのエンジニアが、緯度経度から住所を特定する機能開発の苦労と解決策を綴る。
当初は外部API利用を検討したが、日本の住所の複雑さとAPIの精度問題に直面。
最終的に国土地理院の「位置参照情報」を活用し、自社DB構築とGeohashによるキャッシュ戦略で精度100%を実現。
コストと精度のバランスを取りながら、ユーザー体験を重視した開発プロセスが語られる。
🐸 なぜ今、Agentic Workflowなのか - Graflowの設計思想
AIエージェント活用の課題を解決する「Graflow」の設計思想。
完全自律型(Type C)の制御難しさから、構造化オーケストレーションと局所的自律性を両立するAgentic Workflow(Type B)に特化。
既存ツール(LangGraph等)と比較し、柔軟性と制御性のバランスを重視、SuperAgentをFatノードとして扱い、ワークフローのタスク連携に集中する。
実行時の動的制御も可能にする。

🐸 なぜ今、Agentic Workflowなのか - Graflowの設計思想
AIエージェント活用の課題を解決する「Graflow」の設計思想。
完全自律型(Type C)の制御難しさから、構造化オーケストレーションと局所的自律性を両立するAgentic Workflow(Type B)に特化。
既存ツール(LangGraph等)と比較し、柔軟性と制御性のバランスを重視、SuperAgentをFatノードとして扱い、ワークフローのタスク連携に集中する。
実行時の動的制御も可能にする。
runtime/secret でGoのランタイムから秘匿情報を消す
Goのランタイムに`runtime/secret`パッケージが追加され、秘匿情報を扱うための`secret.Do`関数が導入された。
この関数は、引数として渡された関数内のスタックメモリを消去することで、パスワードなどの機密情報の漏洩を防ぐ。
ただし、現時点ではLinuxのamd64とarm64アーキテクチャのみでサポートされており、いくつかの制限事項がある。
実験では、`secret.Do`を使用することで、コアダンプからパスワードを読み取ることを防ぐ効果が確認された。

runtime/secret でGoのランタイムから秘匿情報を消す
Goのランタイムに`runtime/secret`パッケージが追加され、秘匿情報を扱うための`secret.Do`関数が導入された。
この関数は、引数として渡された関数内のスタックメモリを消去することで、パスワードなどの機密情報の漏洩を防ぐ。
ただし、現時点ではLinuxのamd64とarm64アーキテクチャのみでサポートされており、いくつかの制限事項がある。
実験では、`secret.Do`を使用することで、コアダンプからパスワードを読み取ることを防ぐ効果が確認された。
初老を超えたエンジニアの現実2025
この記事は、40~50代のエンジニアが直面する現実的な変化について、筆者自身の経験を交えながら綴ったものです。
技術の進化は刺激になる一方、モチベーションの維持や集中力の低下、障害への恐怖といったメンタル面の課題も存在します。
AIの活用は助けになるものの、人間が担うべき役割(ステークホルダーとの調整、仕様の理解、謝罪など)は残るでしょう。
休養の重要性やキャリアにおける自身の立ち位置、そして相続税への心配など、人間味あふれる内容を通して、変化し続ける環境下でエンジニアとしてどう向き合っていくかを考察しています。

初老を超えたエンジニアの現実2025
この記事は、40~50代のエンジニアが直面する現実的な変化について、筆者自身の経験を交えながら綴ったものです。
技術の進化は刺激になる一方、モチベーションの維持や集中力の低下、障害への恐怖といったメンタル面の課題も存在します。
AIの活用は助けになるものの、人間が担うべき役割(ステークホルダーとの調整、仕様の理解、謝罪など)は残るでしょう。
休養の重要性やキャリアにおける自身の立ち位置、そして相続税への心配など、人間味あふれる内容を通して、変化し続ける環境下でエンジニアとしてどう向き合っていくかを考察しています。
クロックパズルを単因子論で解く
この記事は、時計の針を揃えるパズルを単因子論という数学の理論を使って解くことを試みるものです。
パズルは、複数の時計の針を、ボタン操作によって全て0を指すように揃えるというもので、ゲームなどにも類似のものが存在します。
記事では、時計の状態を数学的に表現し、ボタン操作を行列で表します。
そして、この問題を解くために、行列を基本変形によってスミス標準形に変形する単因子論の考え方を適用します。
スミス標準形を用いることで、パズルの解を求めるための線形方程式を解くことに帰着できると説明しています。

クロックパズルを単因子論で解く
この記事は、時計の針を揃えるパズルを単因子論という数学の理論を使って解くことを試みるものです。
パズルは、複数の時計の針を、ボタン操作によって全て0を指すように揃えるというもので、ゲームなどにも類似のものが存在します。
記事では、時計の状態を数学的に表現し、ボタン操作を行列で表します。
そして、この問題を解くために、行列を基本変形によってスミス標準形に変形する単因子論の考え方を適用します。
スミス標準形を用いることで、パズルの解を求めるための線形方程式を解くことに帰着できると説明しています。
GraphQLを採用するか迷ったときに読む記事
GraphQL採用の判断材料として、メリットとデメリットをまとめた記事。
メリットは、柔軟なデータ取得、過剰フェッチの抑制、型共有、充実した周辺ツール。
デメリットは、学習コストの高さ、キャッシュ・監視の複雑さ、N+1問題、記述量の増加、エラーハンドリングの煩雑さ、ファイルアップロードの難しさ。
REST APIとの比較を通して、GraphQLが向く・向かないケースを見極める重要性を説いている。

GraphQLを採用するか迷ったときに読む記事
GraphQL採用の判断材料として、メリットとデメリットをまとめた記事。
メリットは、柔軟なデータ取得、過剰フェッチの抑制、型共有、充実した周辺ツール。
デメリットは、学習コストの高さ、キャッシュ・監視の複雑さ、N+1問題、記述量の増加、エラーハンドリングの煩雑さ、ファイルアップロードの難しさ。
REST APIとの比較を通して、GraphQLが向く・向かないケースを見極める重要性を説いている。
緯度経度からの住所検索!〜日本の住所に絶望し、希望を見つけるまで〜
LayerXのエンジニアが、緯度経度から住所を特定する機能開発の苦労と解決策を綴る。
当初は外部API利用を検討したが、日本の住所の複雑さとAPIの精度問題に直面。
最終的に国土地理院の「位置参照情報」を活用し、自社DB構築とGeohashによるキャッシュ戦略で精度100%を実現。
コストと精度のバランスを取りながら、ユーザー体験を重視した開発プロセスが語られる。

緯度経度からの住所検索!〜日本の住所に絶望し、希望を見つけるまで〜
LayerXのエンジニアが、緯度経度から住所を特定する機能開発の苦労と解決策を綴る。
当初は外部API利用を検討したが、日本の住所の複雑さとAPIの精度問題に直面。
最終的に国土地理院の「位置参照情報」を活用し、自社DB構築とGeohashによるキャッシュ戦略で精度100%を実現。
コストと精度のバランスを取りながら、ユーザー体験を重視した開発プロセスが語られる。
シフトレフトは施策ではない --- 品質の作り込みは最初から始まっている
この記事は「シフトレフト」の本質を、単なる工程の前倒しではなく、問題の芽を原因段階で潰す考え方だと整理しています。
曖昧な仕様や前提のまま開発を進めると後工程で高コストになるため、実装前にモデリングで整合性を検証し、不確実性を排除することが重要だと説きます。
具体的には、リソースとイベントを洗い出し、それらが連鎖した際に破綻しないかを確認。
UIは要求を具体化するツールとして活用しつつも、業務上の事実としてモデルに翻訳することを推奨しています。

シフトレフトは施策ではない --- 品質の作り込みは最初から始まっている
この記事は「シフトレフト」の本質を、単なる工程の前倒しではなく、問題の芽を原因段階で潰す考え方だと整理しています。
曖昧な仕様や前提のまま開発を進めると後工程で高コストになるため、実装前にモデリングで整合性を検証し、不確実性を排除することが重要だと説きます。
具体的には、リソースとイベントを洗い出し、それらが連鎖した際に破綻しないかを確認。
UIは要求を具体化するツールとして活用しつつも、業務上の事実としてモデルに翻訳することを推奨しています。
runtime/secret でGoのランタイムから秘匿情報を消す
Goの新しい機能`runtime/secret`は、秘匿情報を扱う際に、スタックやヒープメモリを消去することで、セキュリティを高めることを目的としています。
`secret.Do`関数で囲んだ処理において、パスワードなどの機密情報がコアダンプから漏洩するのを防ぐ効果が確認されています。
ただし、現時点ではLinuxのamd64とarm64アーキテクチャのみで動作し、グローバル変数やgoroutine、ポインタ経由の情報には保護が及ばないなどの制限があります。

runtime/secret でGoのランタイムから秘匿情報を消す
Goの新しい機能`runtime/secret`は、秘匿情報を扱う際に、スタックやヒープメモリを消去することで、セキュリティを高めることを目的としています。
`secret.Do`関数で囲んだ処理において、パスワードなどの機密情報がコアダンプから漏洩するのを防ぐ効果が確認されています。
ただし、現時点ではLinuxのamd64とarm64アーキテクチャのみで動作し、グローバル変数やgoroutine、ポインタ経由の情報には保護が及ばないなどの制限があります。
テセウスのTransformer
この記事は、大規模言語モデル(LLM)の基盤であるTransformerの構造と進化について解説しています。
オリジナルのTransformerと現在のLLMで使われる構造の違い、特にResidual接続やNormalizationの位置の違いを指摘し、学習の可否や高速化、性能向上を目指した各モジュールの研究動向を説明しています。
Transformerは様々な改修を重ねており、どこまで変化したらTransformerとは呼べなくなるのかという問いかけで締めくくられています。

テセウスのTransformer
この記事は、大規模言語モデル(LLM)の基盤であるTransformerの構造と進化について解説しています。
オリジナルのTransformerと現在のLLMで使われる構造の違い、特にResidual接続やNormalizationの位置の違いを指摘し、学習の可否や高速化、性能向上を目指した各モジュールの研究動向を説明しています。
Transformerは様々な改修を重ねており、どこまで変化したらTransformerとは呼べなくなるのかという問いかけで締めくくられています。
View TransitionでわかるNext.jsとAstroの設計思想
この記事では、Next.jsとAstroがView Transition APIをどのように実装しているかを比較し、両者の設計思想の違いを解説しています。
AstroはDOM駆動でMPAの簡潔さを保ちつつSPAのような体験を、Next.jsは状態駆動でReactの機能を最大限に活用して実現しています。
Astroは将来のウェブ標準に準拠するPolyfill的なアプローチ、Next.jsは標準APIを統合し独自のUXを提供するアプローチを取っており、そのコントラストが浮き彫りになっています。

View TransitionでわかるNext.jsとAstroの設計思想
この記事では、Next.jsとAstroがView Transition APIをどのように実装しているかを比較し、両者の設計思想の違いを解説しています。
AstroはDOM駆動でMPAの簡潔さを保ちつつSPAのような体験を、Next.jsは状態駆動でReactの機能を最大限に活用して実現しています。
Astroは将来のウェブ標準に準拠するPolyfill的なアプローチ、Next.jsは標準APIを統合し独自のUXを提供するアプローチを取っており、そのコントラストが浮き彫りになっています。
AIの力を借りて2人で10人分の仕事をする (2025年・個人開発)
この記事は、個人開発の2人チームがAIを活用し、10人分の仕事をこなす方法を紹介しています。
開発、マーケティング、品質保証、分析の各分野でAIを導入し、引き継ぎ、タスク管理、ブログ作成、コードレビュー、テスト、データ集計などを効率化。
AIによって、本来手間のかかる作業を自動化・支援することで、開発チームはより本質的な業務に集中し、生産性を高めることを目指しています。

AIの力を借りて2人で10人分の仕事をする (2025年・個人開発)
この記事は、個人開発の2人チームがAIを活用し、10人分の仕事をこなす方法を紹介しています。
開発、マーケティング、品質保証、分析の各分野でAIを導入し、引き継ぎ、タスク管理、ブログ作成、コードレビュー、テスト、データ集計などを効率化。
AIによって、本来手間のかかる作業を自動化・支援することで、開発チームはより本質的な業務に集中し、生産性を高めることを目指しています。
Claude Codeのコンテキストを節約する
この記事は、AIコーディングツールClaude Code利用時のコンテキスト不足問題とその解決策について述べています。
著者は、コンテキスト使用量を確認する`/context`コマンドで自身の使用状況を調べ、無駄なMCPサーバーの停止、自作MCPサーバーのトークン削減、不要なメモリファイルの削除を行うことで、コンテキスト使用量を大幅に削減することに成功しました。
コンテキスト不足に悩む人や、MCPサーバー・プラグインを多く利用している人に向けて、`/context`コマンドでの確認と、同様の対策を推奨しています。

Claude Codeのコンテキストを節約する
この記事は、AIコーディングツールClaude Code利用時のコンテキスト不足問題とその解決策について述べています。
著者は、コンテキスト使用量を確認する`/context`コマンドで自身の使用状況を調べ、無駄なMCPサーバーの停止、自作MCPサーバーのトークン削減、不要なメモリファイルの削除を行うことで、コンテキスト使用量を大幅に削減することに成功しました。
コンテキスト不足に悩む人や、MCPサーバー・プラグインを多く利用している人に向けて、`/context`コマンドでの確認と、同様の対策を推奨しています。
詳解 筑波大学学園祭を支えた本番ネットワークインフラ全貌
筑波大学学園祭実行委員会が、約4万人が来場する大規模な学園祭を支えるために構築したネットワークインフラの詳細を解説。
大学の光ファイバー網を借用し、自前で敷設工事も行い、最大40Gbpsの高速回線を構築。
3つのステージと移動配信を含む4映像同時配信体制を実現し、トラフィックはダウンロード1.2TB、アップロード3.3TBに達した。
省力化のため、遠隔操作可能なカメラも導入し、インフラ構築の全貌を公開している。

詳解 筑波大学学園祭を支えた本番ネットワークインフラ全貌
筑波大学学園祭実行委員会が、約4万人が来場する大規模な学園祭を支えるために構築したネットワークインフラの詳細を解説。
大学の光ファイバー網を借用し、自前で敷設工事も行い、最大40Gbpsの高速回線を構築。
3つのステージと移動配信を含む4映像同時配信体制を実現し、トラフィックはダウンロード1.2TB、アップロード3.3TBに達した。
省力化のため、遠隔操作可能なカメラも導入し、インフラ構築の全貌を公開している。
詳解 筑波大学学園祭を支えた本番ネットワークインフラ全貌
筑波大学学園祭実行委員会の間瀬bb氏ら3名チームが、約4万人規模の「雙峰祭」でネットワークインフラを構築した全貌を伝える記事です。
4映像同時生配信、人手不足、広大な敷地という課題に対し、大学光ファイバーの借用と自前敷設で本部と各ステージ間を40Gbpsで結ぶ高速ネットワークを実現しました。
インターネット接続は2系統で確保し約3.3TBのアップロードを処理。
IP映像伝送やPTZカメラ遠隔操作を導入し、配信作業を省力化するなど、学生の技術と工夫で大規模イベントを支えた挑戦が詳細に語られています。

詳解 筑波大学学園祭を支えた本番ネットワークインフラ全貌
筑波大学学園祭実行委員会の間瀬bb氏ら3名チームが、約4万人規模の「雙峰祭」でネットワークインフラを構築した全貌を伝える記事です。
4映像同時生配信、人手不足、広大な敷地という課題に対し、大学光ファイバーの借用と自前敷設で本部と各ステージ間を40Gbpsで結ぶ高速ネットワークを実現しました。
インターネット接続は2系統で確保し約3.3TBのアップロードを処理。
IP映像伝送やPTZカメラ遠隔操作を導入し、配信作業を省力化するなど、学生の技術と工夫で大規模イベントを支えた挑戦が詳細に語られています。
Claude Code × MCP × Notion で「Jupyter Notebookから分析レポート」ことはじめ
Jupyter Notebookで作成されたデータ分析結果を、生成AI(Claude Code)と連携プロトコル(MCP)を用いて、社内ナレッジツールであるNotionに高品質な分析レポートとして自動生成する手法を検証し、Notebookを負債ではなく資産として残すことを目指している。

Claude Code × MCP × Notion で「Jupyter Notebookから分析レポート」ことはじめ
Jupyter Notebookで作成されたデータ分析結果を、生成AI(Claude Code)と連携プロトコル(MCP)を用いて、社内ナレッジツールであるNotionに高品質な分析レポートとして自動生成する手法を検証し、Notebookを負債ではなく資産として残すことを目指している。