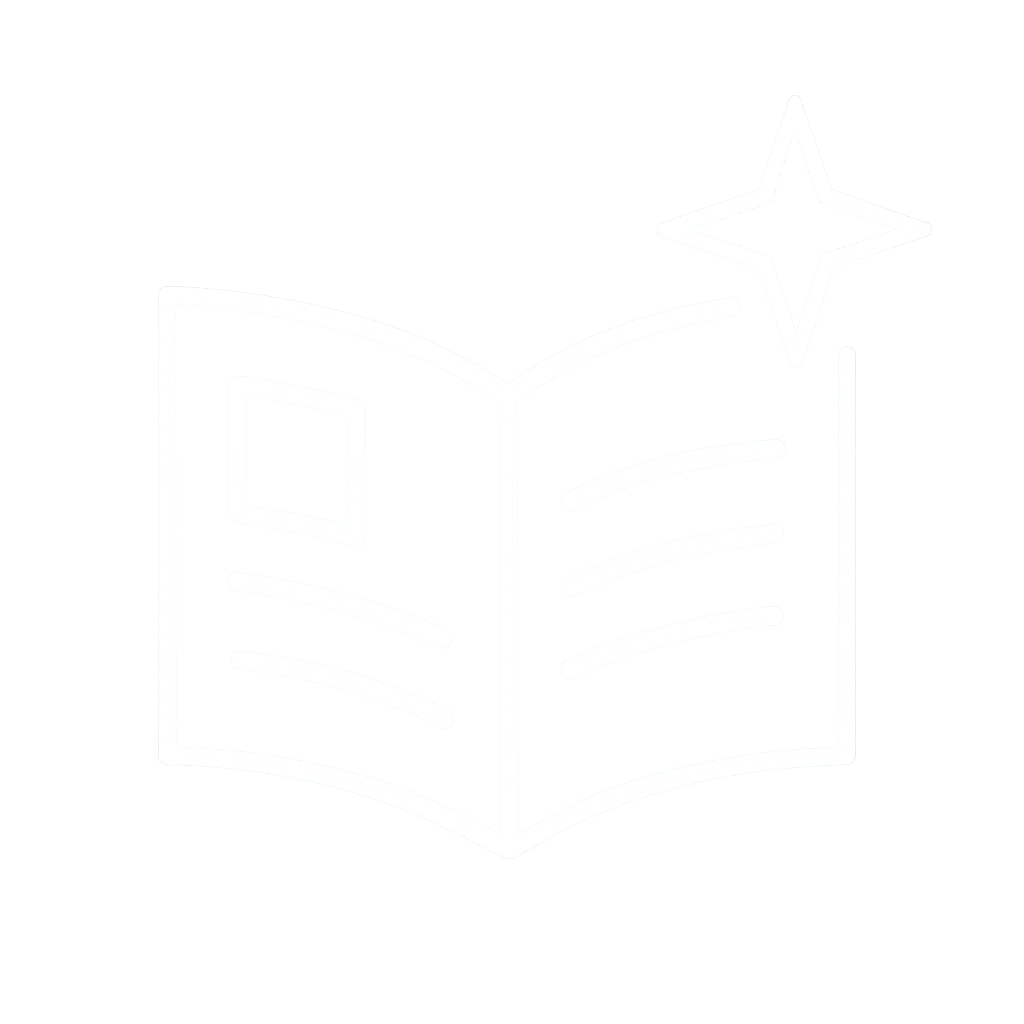Yamatonchu
@yamatonchu.bsky.social
5 followers
0 following
1.4K posts
論語はじめ現代において意訳・誤訳で訳出された内容が通説になっている古代漢文書籍を文法的に正しく翻訳して読んでみようという事で
古事記を現在は翻訳中です。
Posts
Media
Videos
Starter Packs