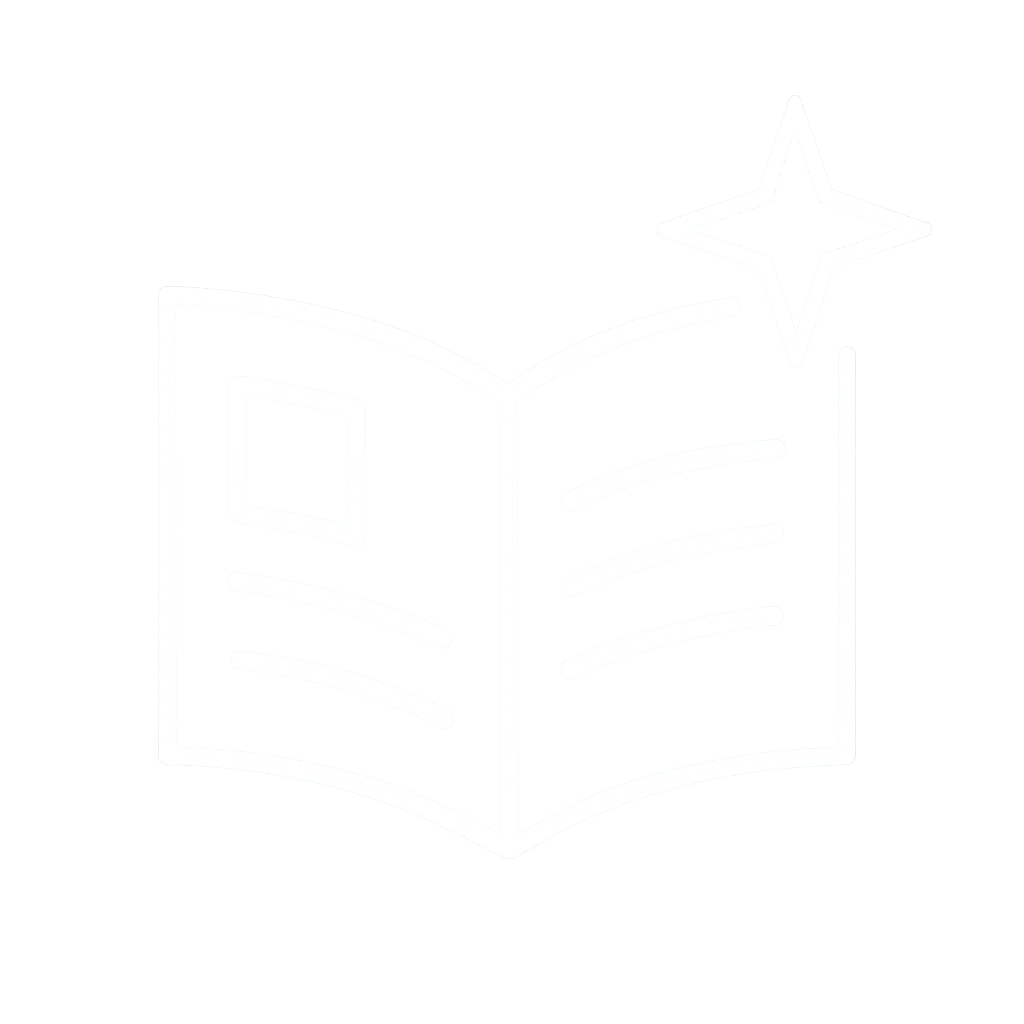名古屋市名東区 渡辺内科
@watanai.bsky.social
0 followers
1 following
59 posts
名古屋市の開業医。気付いたこと、思いついたこと、感銘を受けた言葉、ちょっといい話、音楽や絵画のこと、そして専門である循環器内科や一般内科を含む医学や医療のことなど、種々雑多なことをメモします。
2011年10月からX(旧ツイッター)を利用していましたが、2025年10月10日をもってBlue Sky(ブルースカイ)に引っ越しました。
X(旧ツイッター) 現在リツイートのみ
https://x.com/watanabenaika
渡辺内科 HP
https://watanai.jimdofree.com/
Posts
Media
Videos
Starter Packs