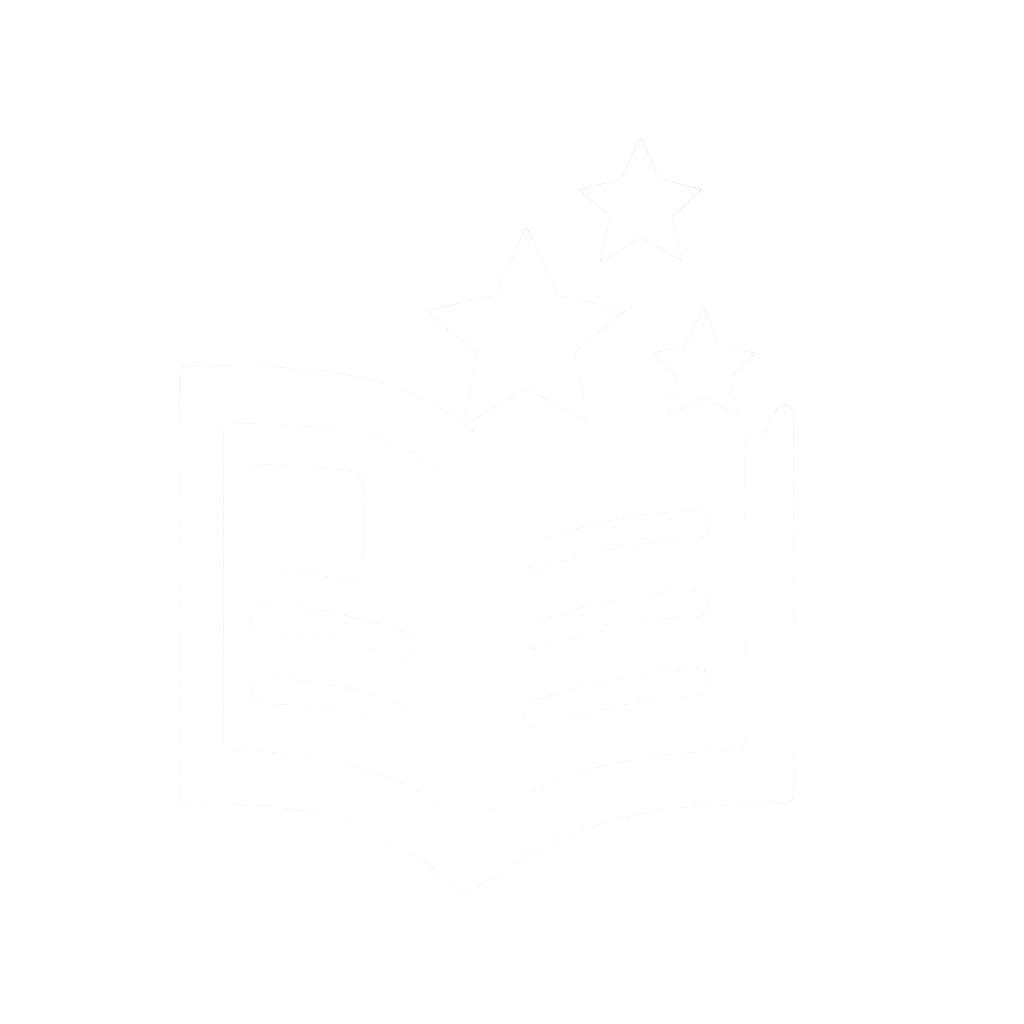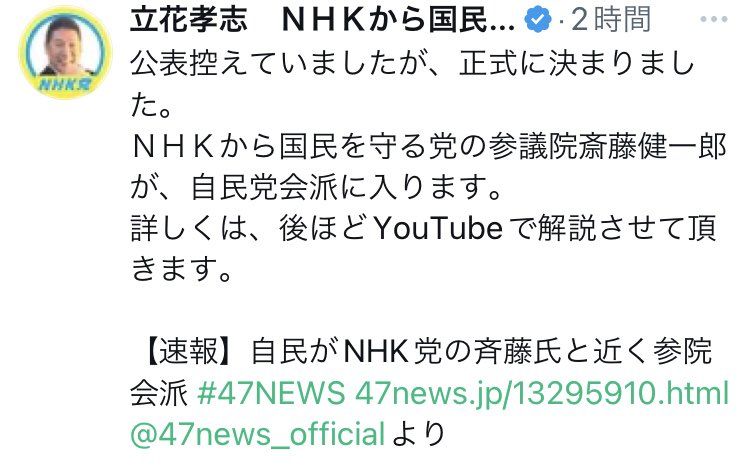高橋誠一郎
@stakaha8.bsky.social
400 followers
57 following
2.6K posts
近著『黙示録の世界観と対峙する』(群像社)では比較文学と比較文明論の手法で『悪霊』などドストエフスキー作品と日本の文学における黙示録の問題を考察しています。そのことにより第三次世界大戦を望む教団と政治との癒着の危険性に迫りました。主な著書に『堀田善衞とドストエフスキー』、『「罪と罰」の受容と立憲主義の危機』など。
ホームページ stakaha5.jimdofree.com
旧ツイッター https://x.com/stakaha5
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎
Reposted by 高橋誠一郎