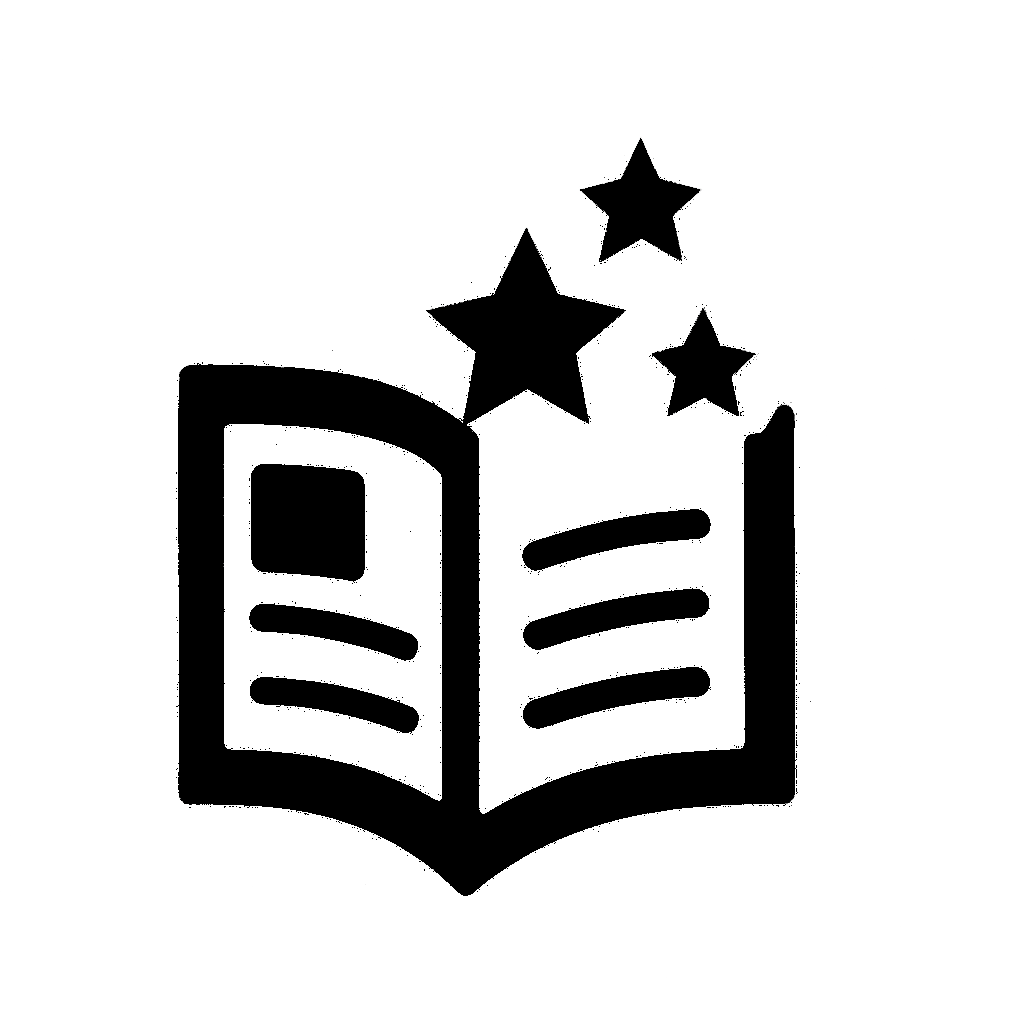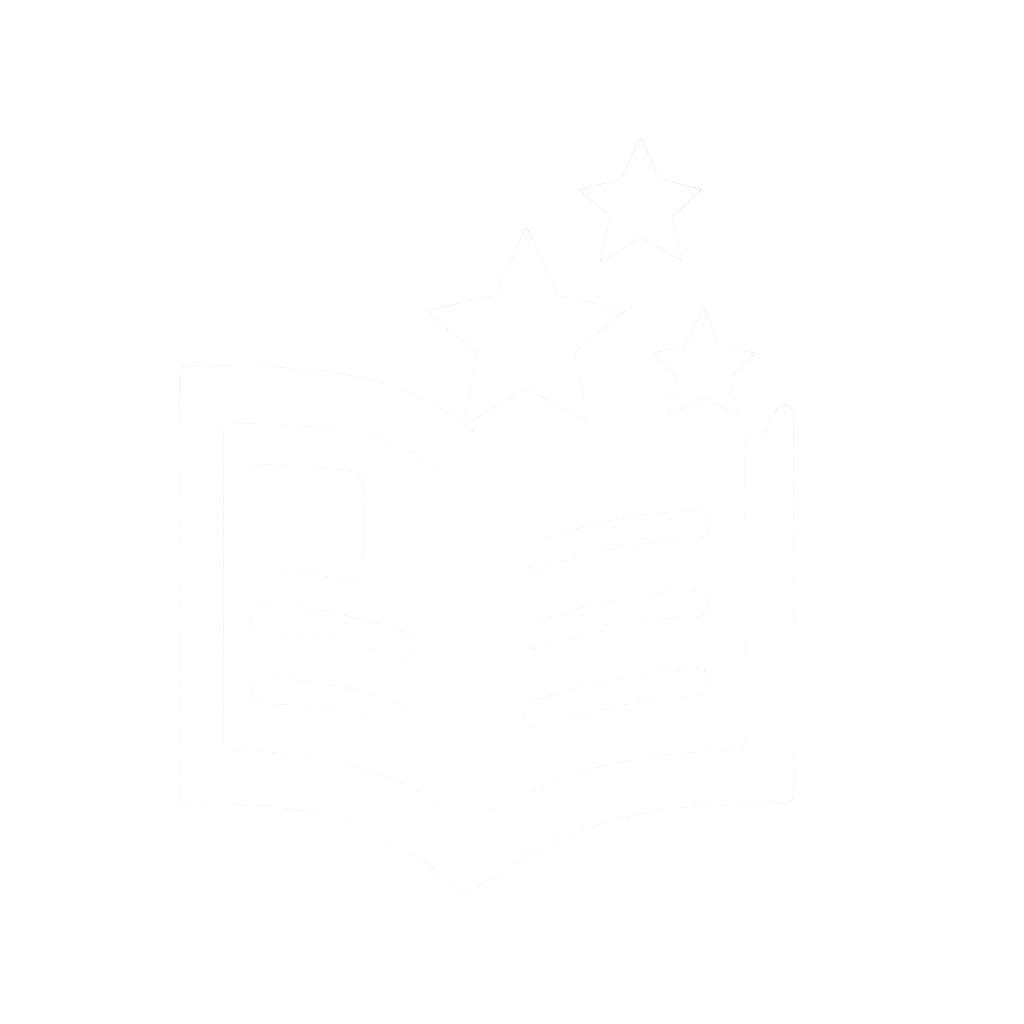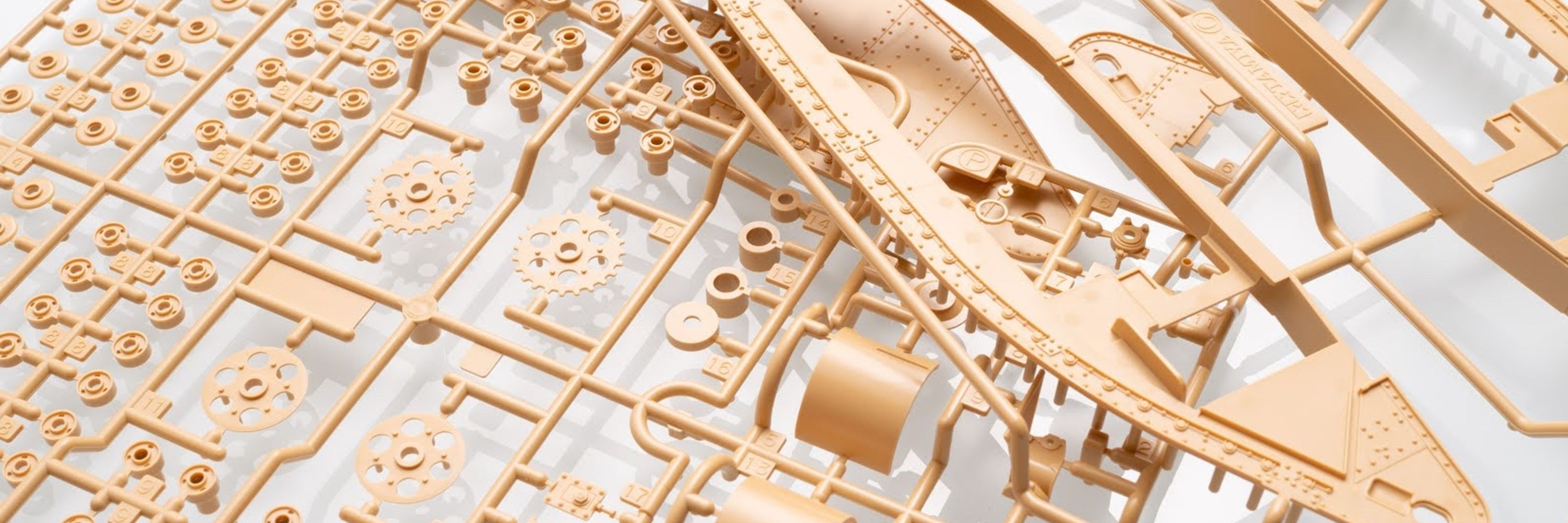
nippper.com
@nippper.bsky.social
550 followers
520 following
690 posts
すべての人とプラモデルの楽しさをシェアする投稿サイト『http://nippper.com』の公式アカウントです(pは3つです!)。プラモデルの素晴らしさを世界に伝える皆さんの寄稿を常にお待ちしております。寄稿方法は以下のページからどうぞ!→http://nippper.com/2020/01/14498/
Posts
Media
Videos
Starter Packs