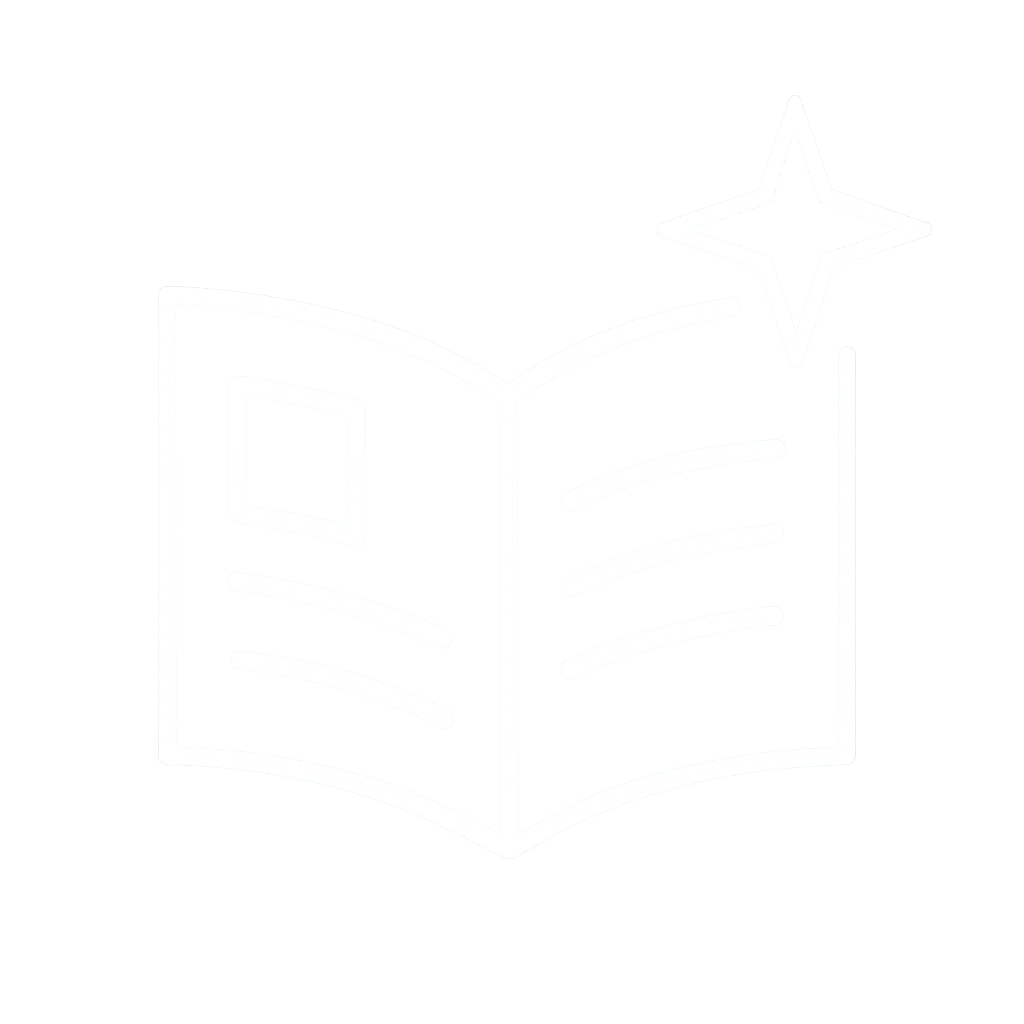二本松哲也
@nihonmatsu.bsky.social
140 followers
83 following
4K posts
考えるセキュリティ、伝えるインテリジェンス。
能動的サイバー防御 / Security & Privacy by Design / IPCC report communicator
※個人の見解であり、所属組織とは無関係です。
👉 友人のWeb制作会社WEBDEAをよろしく!
Posts
Media
Videos
Starter Packs
二本松哲也
@nihonmatsu.bsky.social
· 10h
二本松哲也
@nihonmatsu.bsky.social
· 10h