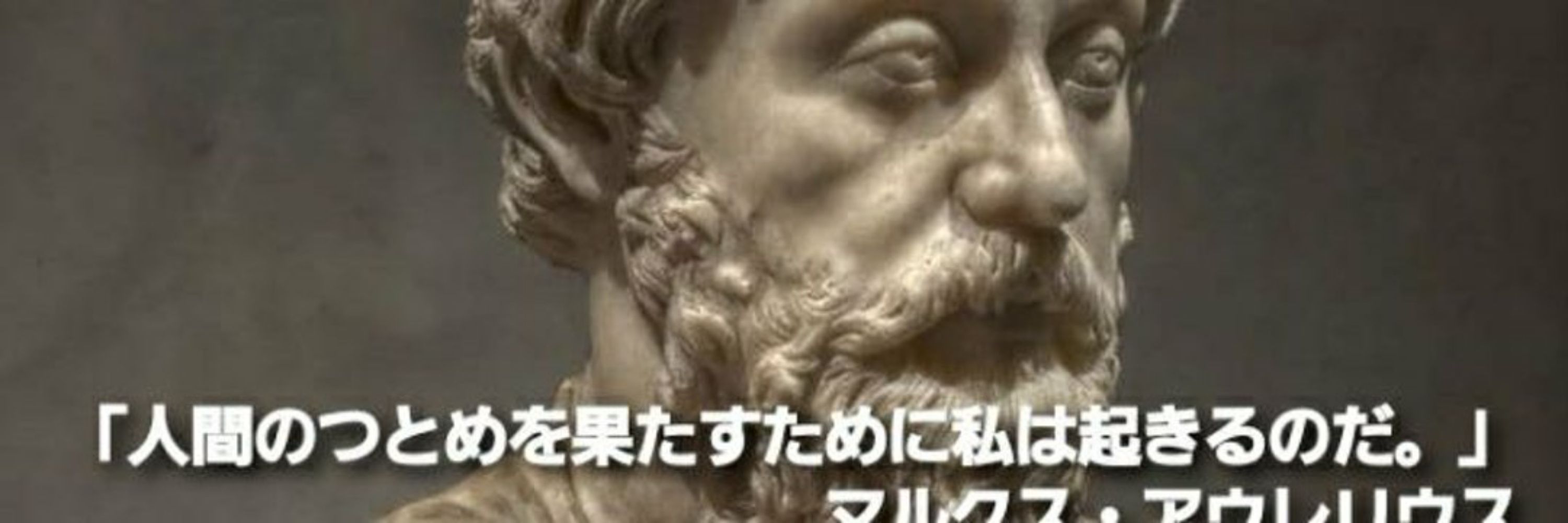
まさ
@careworker.bsky.social
47 followers
53 following
1.3K posts
哲学に関心のある介護職。
介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士。
Discordにて読書会「ケアとか倫理とか哲学とか」主宰/9月14日(日)22時~
第10回フランクル読書会/27日(土)22時~
第31回レヴィナス読書会
高卒。哲学・倫理学の専門教育は受けていません。
Posts
Media
Videos
Starter Packs
Pinned
まさ
@careworker.bsky.social
· Jan 24
Reposted by まさ
まさ
@careworker.bsky.social
· 10d
まさ
@careworker.bsky.social
· 10d
まさ
@careworker.bsky.social
· 10d
まさ
@careworker.bsky.social
· 10d







