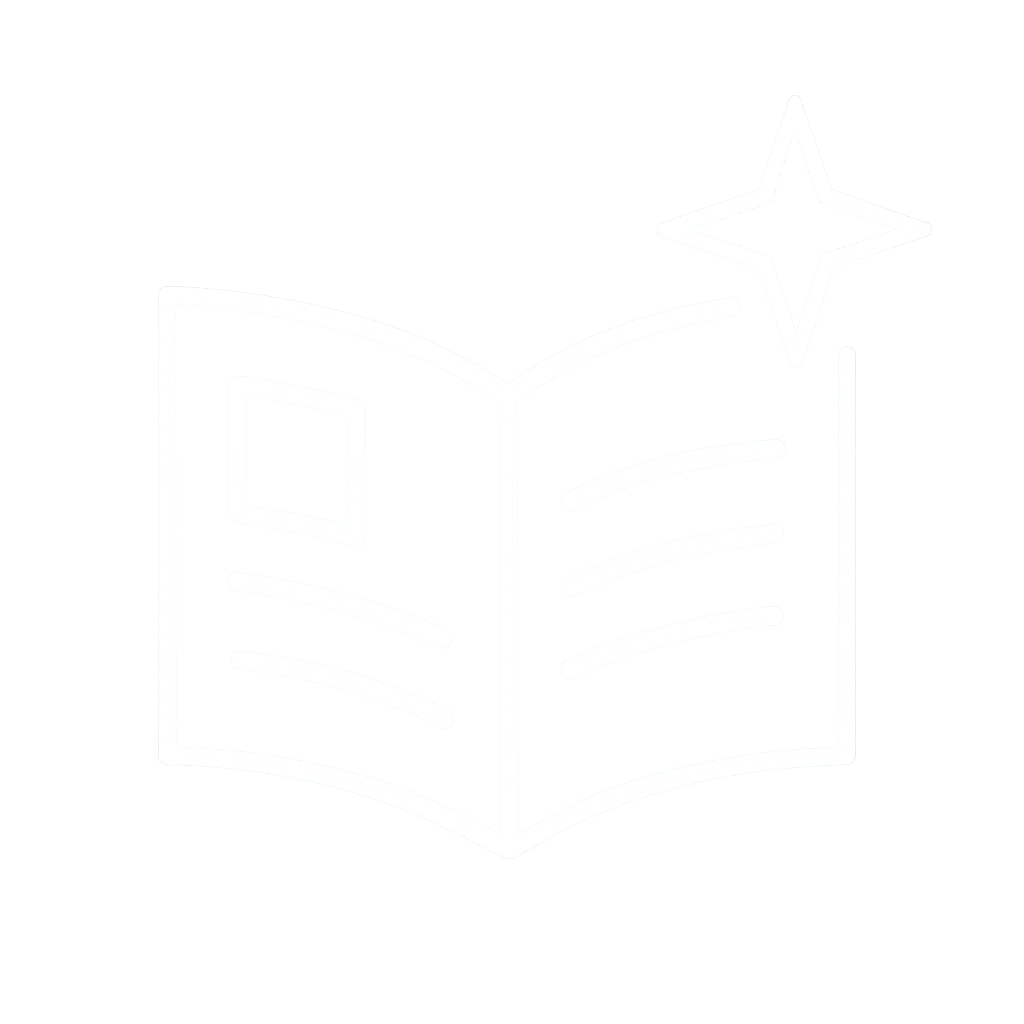ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
120 followers
24 following
310 posts
読んだ本のことなど書いています。
Posts
Media
Videos
Starter Packs
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· 20d
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· 20d
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· 22d
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· 22d
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 31
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 31
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 25
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 25
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 25
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 20
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 20
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Aug 20
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Jul 16
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Jul 10
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Jul 10
6月までに読んだ本のうち、特に好きだった10冊。読んだ順です。
#2025年上半期の本ベスト約10冊
◆『美は傷』エカ・クルニアワン
◆『チャーチ・レディの秘密の生活』ディーシャ・フィルヨー
◆『この村にとどまる』マルコ・バルツァーノ
◆『わたしたちが光の速さで進めないなら』キム・チョヨプ
◆『チェーンギャング・オールスターズ』ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー
◆『密やかな炎』セレステ・イング
◆『ブリス・モンタージュ』リン・マー
◆『歌う丘の聖職者』ニー・ヴォ
◆『極北の海獣』イーダ・トゥルペイネン
#2025年上半期の本ベスト約10冊
◆『美は傷』エカ・クルニアワン
◆『チャーチ・レディの秘密の生活』ディーシャ・フィルヨー
◆『この村にとどまる』マルコ・バルツァーノ
◆『わたしたちが光の速さで進めないなら』キム・チョヨプ
◆『チェーンギャング・オールスターズ』ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー
◆『密やかな炎』セレステ・イング
◆『ブリス・モンタージュ』リン・マー
◆『歌う丘の聖職者』ニー・ヴォ
◆『極北の海獣』イーダ・トゥルペイネン

ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Jul 7
ユキ
@yukimemo2020.bsky.social
· Jul 7