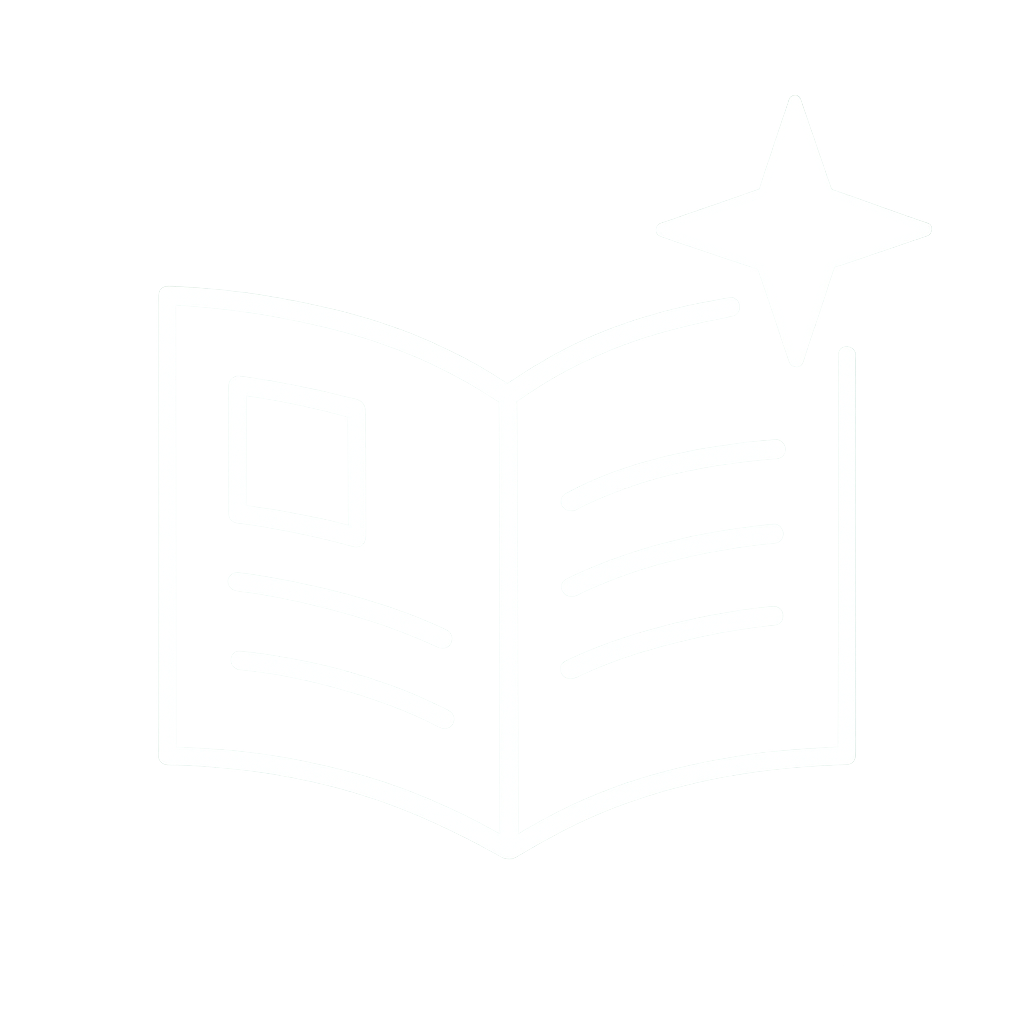憂理
@yorunoyuri.bsky.social
42 followers
53 following
260 posts
君と私で月に帰る。言葉を散らして月光を摘み取る。詩の死骸を掻き集める。
Posts
Media
Videos
Starter Packs
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 22h
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 12d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 13d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 15d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 17d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 20d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 22d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 25d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· 29d
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Oct 1
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 27
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 25
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 23
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 20
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 18
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 16
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 14
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 11
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 8
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 5
憂理
@yorunoyuri.bsky.social
· Sep 3